流星群











ごめんね。
しんと凍えた天高く、巨大な白い花が崩れゆく。
仰ぐ先、吐き出す白い息の向こうに、幾つもの放射を描いて散る流星群。
降り注ぐのは、心の、魂のかけら。
ごめんね。
輝く欠片を浴びながら、それらを喰らい尽しながら。
腕にあるちいさく愛しい命を、抱きしめた。

「ジジイのところへ行け」
背には深く豊かな森。
輝く水平線をじっと見据えながら、不意に友が言った。
海に臨む崖の縁に長い時間黙って座り込んでいるものだから、心配でようすを見にきたところだったのだ。だから一瞬、なにを言われたのか理解できなかった。
ゆっくりと目のまえで、王宮の奥にある鳩の血色をした紅玉で紡いだ絹糸のような長い髪が、金の光を絡ませながら揺れる。
え、と短く訊き返すと、いつもとおなじ幼子の姿のまま、いつもとは違う氷のように冷たく低い声音で、
「おまえにいて欲しくはない」
ちいさな肩越しにこちらを振り返った、金の輻射が走る紅玉の瞳。
燃え盛る炎のような色合いの、けれどそれとは相反するあまりに低い温度のそれに、身体ごと心が震えて、手にしていた果実を落としてしまう。
音を立てて地面に落ちて転がる果実を一瞥した友は、ゆらりと立ち上がると、使いを出す、と突き放すように短く言ってこちらに背を向けた。
リュシーダサンイ。
それが友のなまえ。
凍えながら燃える炎、有翼の赤き月、純粋なる世界の鏡、と幾つもの呼び名を持つ友は、神秘の力を得て凝った夜闇から発生する魔族の、その王たる存在だった。
「……え?」
対して、突然の拒絶にわけがわからずその後さえ追えずにただ立ち尽くすのは、ただの人間。それもなんの力も持たないちっぽけな、性別すら持たない不完全な存在だ。
それでも、ケイ・イーリィは魔王が直接統べるマラシトという名の島に、ただひとり留まることを許された人間で、世界の半分を凍れる炎で支配する魔王は、つい最近まで外の世界を知らなかったケイにとっては親しみやすくも頼りになる、生まれてはじめてのたいせつな友だった。
種を超えて互いを思い合いながらこの魔族の王都でずっと楽しく暮らしていけると、そう信じていたのだ。
ケイは思いがけない拒絶にしばらく呆然としていたが、やがてじわじわとそれを頭で理解しはじめると、ほんのちいさな子どものように泣き出しそうになった。
頭でわかっても、心がそれを拒否するのだ。
冗談だよ、といつものように明るい笑顔で言って欲しい。そう言ってくれると信じたい。
ジジイ、というのはケイが生まれた国ミリード一番の魔法使いのことだ。血の繋がりなどはないが、離れて暮らしているこちらを心配して月に何度も連絡を寄こしてくる。
その老魔法使いのところに行くのが嫌なのではない。
そうではないのだ。
気付くと、ケイの足は走りだしていた。思い切り走ったことなどない足はよたよたと頼りないけれど、それでも懸命に走る。
だというのに、
「リュー!」
自分よりもずっとちいさな子どもの姿をしている魔王は歩いて去ったというのに、どれだけ走っても追い付くどころかその姿すら見つけることができなかった。
息がきれて、汗が噴き出す。苦しくなって緑の葉を空いっぱいに広げる大樹の幹にすがると、耳のあたりに蜂の羽音のようなものが聞こえた。
見ると、魔王の眷属であるつぶらな瞳が愛らしい竜型の魔族がこちらを見つめている。
「ねえ、リューがどこにいったか、知らない?」
訊ねるが、蜂鳥のように細かく素早く翼を動かして空中に浮くちいさな竜は、ぷるぷると羽毛に包まれた身体ごと首を横に振った。
凍えながら流れる滝のような銀色のこちらの髪で遊びたいのか、頭のまわりを蜂のような音を立てて飛びまわる竜に、ごめんね、と断りつつ頭を撫でて、ケイはふらふらとふたたび走り出した。
「リュー? どこにいるの」
森のなかを走り泉のほうへと向かっても、その姿は見当たらなかった。もしや、と思い青く澄んだ空を見上げてみるが、金色の翼と紅色の飛膜を広げた魔王はいない。
「どこ」
見つけられない、というその事実に心が震えて、顔が歪んだ。
「やだよ……」
瞳の奥が熱くなって、じわりと視界がぼやけた。すると、哀しげな鳴き声があちらこちらから聞こえてくる。
一瞬、リュシーダサンイになにかあったのかと思ったが、すぐに違うと首を振った。
魔族は人の心を映す鏡だ。
眷属たちは、ケイの心を映して泣いているのだ。
彼らはひどく純粋で、目のまえにいる者の喜怒哀楽を映して染まる。そうしておなじように喜び、哀しむのだ。まるで自分のことのように。
だから、ケイはちいさくうめきながらも、陽光に弱いため日除け液を塗っている真白い頬に流れた涙を、ぐい、と拭った。
「泣かない。だいじょうぶ」
言うそばから涙が込み上げてくるが、そのたびに涙を拭い、歪みそうになるくちびるを引き結び、洟を啜る。荒い呼吸のせいなのか、頭は重いし目も眩む。それに目と鼻からは水が出るくせに、喉が干からびそうだった。
しっかりしなくては、と顔を洗うついでに喉を潤そうと、泉の縁に座った。
すると、透明の清い水面に、情けない顔が映る。
身体はひどく熱いというのに、真白い顔は青ざめて見えるほどさらに白くなっているし、いつもは薄紅色の瞳もいまは真っ赤になっていた。
「……うさぎみたい」
たったこれだけのことでいまにも眩暈を起こして倒れてしまいそうな自分に溜息をつくと、水面が揺れて波紋が生まれた。自分の影もぼやけて、水に溶けていく。
また泣きそうになっていると、ふわり、と不意に頭の上に日除けの布を掛けられた。もしかして、と顔を上げる。
「リュー?」
けれど、そこにいたのはリュシーダサンイではなく、うさぎのように長い耳と美しい黒い毛並みを持つその眷属だった。いつも、うさぎさん、と呼びかけているから、魔王の友人に呼ばれたと思って現れたのかも知れない。
「……ありがとう」
無理ににっこり笑ってみせると、黒いうさぎのような魔族は表情こそわからないがどこか辛そうにその身体を震わせた。
「ごめんね? あの……オレ……いないほうが……いいのかな……」
訊ねると、魔族は困ったように首を傾げる。そして、ぴくり、と長い耳を片方だけ高く立て、
「魔王から、伝令」
大抵の魔族は人の言葉を話すことはないが、この魔族は上位にあるものらしく時折人の言葉を話す。それが、鳥が覚えたての人の言葉を話すような拙さで、そう告げた。
「え? リューから? なんてっ?」
「人間の軍隊、来る」
「……え」
「ケイ、ミリード帰る」
「ま、まって……」
「我ら、悪意に染まる」
人間は、弱い。
だから自分たちとは違うものを容易に受け入れない。信じない。わずかな悪意さえも抱えない人間というものは、稀有だ。
魔族に善悪という概念はない。だから、人間にとって悪となることをする魔族もあるだろう。いや、それすらも人間の姿を映し行動した結果であるのかも知れない。そしてなにも知らない人間のなかから、それを討伐しようとするものが現れることは、避けられないことなのかも知れない。それはどうしようもないことなのかも知れない。
けれど、魔族は純粋なる鏡なのだ。
人間の闘志により、魔族は闘争心を煽られる。戦ううちに、人間の心に相手を害しようという気持ちが生まれてくれば、それは悪意に繋がり、その悪意を映した魔族はその悪意をそのまま人間に向けることとなるのだ。
純粋なものほど、穢れやすい。どこまでも、穢れに染まる。
その姿を、見られたくない。
そう言っているのだ。
「戦場、醜悪。危険」
「ねえ、待って! もしかして、リューもそう思ってるの? だからなのっ?」
だから、ジジイのところへ行け、なのか。
誰よりもはやく、遠くで魔族討伐に兵を挙げる人間の動きを感じたから。だから自分の傍にはおけないと判断したのか。
「ケイに一番近い眷属、ケイを連れ、ミリード行く」
そう言ってミリードの魔法使いのもとに使いに行くという耳の長い黒い魔族が、ぐい、と伸び上がりこちらに覆いかぶさってこようとする。それへ、咄嗟に腕を伸ばし、体当たりをする勢いでぶつかっていき、
「ごめん。邪魔させてもらうね」
ぎゃっ、と驚いて声を上げた魔族を両腕で抱え込み、その動きを封じてしまう。
そして、
「あのね、オレ、ちょっとだけ怒ったんだからねっ!」
さきほどまで項垂れていた姿が嘘のように、ケイは颯爽と立ち上った。
魔族がなんであるのかを知らない人間は、多い。
だから、魔族討伐の兵を挙げるのだ。
そして兵士たちは死闘を繰り広げることとなる。目のまえにいる魔族が、おのれの醜い姿そのままを映しているものと知らずに。
人間と魔族、その両者が疲れ果て動けなくなるまで、戦いはつづく。
だがそれは、その場に魔王がいない場合だ。
魔王は王であるがため、おのれを愛し愛する純粋なる眷属たちを守ろうとする。残忍かつ容赦ない恐るべき力で眷属を苦しめる穢れを、滅しようとする。
生まれて間もない不完全な魔王であるならばともかく、おのれの眷属すべての力を食みそれを蓄えた闇を統べる禍々しき神聖の力は圧倒的で、そのまえにおいては歴戦の勇士であろうがなんであろうが、人間などただ目障りなだけの虫けらに過ぎない。
そして、現在魔王の座にあるリュシーダサンイは、生まれて間もない魔王などではなかった。
因って、これからはじまるだろう戦いの場に魔王が現れたその瞬間、兵士たちの未来は消え失せる。
そうして穢れは、排除されるのだ。
それはその戦いに関わった人間が多ければ多いほど、速やかに。
国ごと攻めてくるのならば、その人間の国はたった一夜にして血の海に沈むほどに。
それは、魔王にとっては悪でもなんでもない、ただ、穢れを排除するというだけの行為なのだ。
けれど。
「見せたくないっていうことは、ほんとはそんなことしたくないっていうことだよね」
ケイはまだどこか呆然としているらしい黒い魔族をしっかりと抱え、ちいさくくちびるを噛んだ。
「ねえ、リューは、魔王はいまどこ」
訊ねると、魔族は勢いよく首を振る。その勢いのままに頬を打つ長い耳にもめげず、ケイは質問を繰り返した。
「教えてよ。知ってるんでしょう?」
「教えない」
きゅ、と長い耳を絡ませて縮こまる魔族がすこしかわいそうになって溜息をつくと、黒くてまるい瞳がこちらを見上げる。
「ケイ、ミリード帰る」
繰り返されて、口をひんまげた。
「やだ。言ったでしょ。オレ、怒ってるんだから」
「ケイの悲しい、流れてくる」
そうまっすぐに言われてしまうと、ひんまげたくちびるが震えそうになって困る。違う、と言ったところで、魔族に嘘は通じない。
「リューを止めなきゃ」
「魔王、止まらない。人間の軍隊、止まっていない」
それを聞いて、ケイはちいさく喉に息を飲む。
そう、魔族は鏡。人間が魔族と戦おうとするかぎり、魔族も人間と戦おうとする。人間が魔族と戦うことをやめたなら、魔族も人間と戦うことをやめる。
魔王を止めるなら、人間を止めなくてはならないのだ。
「……わかった。じゃあ、リューの言うとおりにしよう。うさぎさん。オレをミリードのヒゲ爺さんのところに連れてって」
絡まっていた長い耳が勢いよく解かれるさまを見つつ、ケイはこくんとひとつ頷いた。
「オレが軍隊を止めるから!」
人間をとめるのは、人間。
これから起こることを知っていて、なおかつ人間と魔族のどちらとも話ができるのは、自分だけなのだ。
そう自分に言い聞かせて、ケイは抱えた魔族の、思いがけない言葉を聞き呆気にとられて瞠られた、濡れたように光る瞳を見つめる。
人間と魔族の戦いを止めなくては、リュシーダサンイとその眷属が、大切な友がたくさん傷つくのだ。
けれど自分だけでは力が足りない。大きな軍隊を止めるなら、もっと大きな力を借りなくてはならない。ミリードのヒゲ爺さんをはじめとする魔導師たちなら、力を、良い知恵を貸してくれるに違いない。
だから、
「ミリードに、行こう」

ミリードは、四方を山に囲まれた自然豊かな小国だ。
そして、勤勉な民により編み出され研究が続けられている魔術が盛んな国でもある。
その豊かさと魔法力を吸収せんと隣接する国々に長年つけ狙われ続け、何度も崩れかけていた他国との不安定な力の均衡も、近年では山に囲まれているというのに、まるで幾つもの川が流れ込む大きな海のように魔法力が集まり出したことにより、安定してきていた。
だがそれが、ミリード王宮の魔導師と魔王との約束であることを知る者は、少ない。
その、魔王との結びつきあるミリード王宮の、奥深く。
鏡の間と呼ばれる全面が鏡に覆われただけのなにもない部屋へと続く、回廊。
そこに、異変が生じた。
四方八方に黒い稲妻が駆けまわり、火花が散る。そうかと思えば、稲妻と火花とに彩られた回廊に、真白い紙の上に落としたインク染みのように、まるい闇の穴が唐突に生まれ、瞬きする間に人ひとりを丸飲み出来るほどの大きさに広がった。
息も白く凍えるほどに一瞬にして凍結した空間、そこに口をあけた穴の向こうから、銀色に輝く鋭い爪が伸びる。
そしてその爪が穴の縁を掴み、そこから素早く影を脱ぎ捨てるように、巨大な姿が回廊へと飛び出してきたのだ。
「魔族!」
突如現れた闇を切り取ったような漆黒の姿に、回廊を巡回していた衛兵が悲鳴を上げ、その声を聞きつけた者たちが武器を手に慌てて集まり出す。
漆黒の魔族は爛々たる眼光で集まった兵士たちを睥睨し、わずかでも近付こうものなら切り裂いてやるとでもいうように頭に突き出た二本の諸刃の剣を向けている。
全身で威嚇する鋭く恐ろしい魔族の姿に、兵士たちはそれでも震える手で剣や槍を手に囲んだ。
そこへ、
「静まれ! 怯えるな、下がれ!」
人の群れの向こうから凛と命じる声が、響き渡った。
ほっ、と兵士たちの表情にわずか、安堵の色が走る。
「武器を下せ!」
「し、しかし、エゼルレッド様!」
「いいから、下がれ。前にも言っただろう。魔族は鏡だと」
そう言いながら、困惑する兵士たちをかき分け魔導師の法服を揺らして現れた青い瞳の魔法使いに、黒い毛並みをしっかりと掴んだケイはほっと胸を撫で下ろした。
「ルーくん」
巨大な獣の姿に変じた長耳の魔族の背から滑るように下りて声をかけると、十三魔導師のひとりルーサー・エゼルレッドが瞳をまるくしてぽかんと口をあける。
「ケイちゃん?」
ほんとうならば彼はそう簡単に会えないほどの地位にある魔導師ではあるが、相変わらずの寝癖がケイの緊張感を解きほぐす。
彼は、彼の師匠であるヒゲ爺さんことトバイアス・オルブライトとともにケイを助け、そしていまも助けてくれているひとだ。
「ルーくん!」
駆け寄って抱きつくと、エゼルレッドの綺麗な青い瞳が海のように輝いた。
「わぁ、ケイちゃん! ひっさしぶりっスね〜。元気だったっスか? なんか、お師匠様ばっかりケイちゃんに連絡するから、寂しかったっス〜」
油断すると口調が元に戻るのも、嬉しい。
「あれ〜? あの、まお……じゃなくて、リューちゃんはどうしたんスか? きょうは一緒じゃないんスね? あの魔族は、たしかリューちゃんの側近みたいなコだったような」
こちらの銀色に流れる髪をぐりぐりと嬉しそうに撫でながらも、警戒して針のように逆立てていた毛を落ち着かせ、頭の剣を一振りしていつも通りの長耳に戻した魔族を見遣り、あれ、と首を傾げるエゼルレッドに、ケイも笑顔をひっこめた。
いまは、再会を無邪気に喜んでいる場合ではない。
ケイは微笑む魔法使いを見上げて、薄紅色の必死の双眸で訴えた。
「ルーくん、聞いて! リューが、魔王が怒ってるの!」
「うん?」
「軍隊を止めてっ!」
お願い、と声を絞り出すように言うと、法服を握りしめて白くなった手指をやさしく掴みとられる。そして、
「お師匠様に、ケイ・イーリィと魔王の側近が来たことを伝えろ。それから、フラムスティードとレイブンズクラフトにマラシト海上へ物見をやるように。非番だが叩き起こせ。スワンさん、レヴィさんにはいつでも出られるように。緊急事態だ、急げ」
そう背後を振り返って指示したエゼルレッドに、
「ケイちゃんはとりあえず、落ち着こうか」
慌てふためき駆けて行く兵士たちを背に、ね、と微笑まれて、泣かないと決めていたのに呆気なく涙腺が決壊した。
顔を涙と鼻水でぐしゃぐしゃにして何度もつっかえながら、リュシーダサンイにミリードへ帰れ、と言われたこと、人間の軍隊がマラシトへ進軍してきていることを伝えると、しゃくり上げて苦しい胸を宥めるようにエゼルレッドの大きな手で背を擦られる。
怯えや敵意を持つ人間がこの場にいなくなったことで身体を元の大きさに縮ませた漆黒の魔族は、長い耳を揺らしてすり寄ってきた。哀しげに鼻を鳴らすその様子に、ケイは泣き声を飲み込み、洟を啜り上げる。
そろそろと胸から息を吐き出すと、泣きすぎてぼんやりした頭に色が戻ってきた。
「ちょっと落ち着いた?」
上等の法服の袖で顔を拭かれて、びっくりする。けれどエゼルレッドは気にせず、にこりと笑った。そして、ゆっくりと表情を引き締め、
「それで……リューちゃんがミリードに帰れ、って言ったのはいつのこと?」
「え?」
「魔王がつくったマラシトからミリードへの『道』を通ってきたなら、そう時間は経っていないだろうけれど」
「あ、えっと……」
正直、時間など気にしてはいなかった。マラシトでリュシーダサンイたちと過ごしている間も、太陽が輝きだしたら起き、月が歌い出したら眠っていたのだ、よくわからない。
困っていると、腕のなかの魔族の黒くまるい瞳が知的に輝いた。
「人間の時間、三時間経過」
「三時間か。それで、魔王がどこにいるのかは、わかる?」
「…………」
「口止めされてるのかな?」
耳を左右に揺らしながらまっすぐに見据えるものの魔王の居場所を口にしない魔族に、エゼルレッドは吐息に苦笑を滲ませる。ケイが不安になって見上げると、困ったように微笑んで頭を撫でてきた。
「大丈夫。リューちゃんのことは、見つけるよ。どこの国が兵を出しているのかも、調べるから。でも、魔王の側近が話してくれたら、はやいんだけどなぁ」
「人間の指図、受けない」
「ケイちゃんのお願いでも駄目なのかなぁ?」
「ケイは、好き。でも、駄目」
「ただでは教えないってことかな、魔族」
「それが世界の理」
こくん、とうなずく魔族に、ケイは薄紅色の双眸をおおきく瞠る。
そういえば、魔王が言っていた。
なにかを望むなら、その望みとおなじだけのなにかを差し出さなくてはならない、と。
それが世界の理なのだ、と。
「え、あの、でも……オレ、リューにいろんなことお願いしてたりしたけど、その、あの、オレはなにも……払ってないよ?」
ケイがこうしていまも自由に生きているのは、魔王とエゼルレッドたちの約束によるものだ。ケイが支払ったものの結果ではない。
リュシーダサンイはケイに関する大抵のことを、無条件に許容していたようにも思える。ケイにはリュシーダサンイになにかを支払った覚えなど、ひとつもなかったのだ。
それ以前に、なにも持っていない。
エゼルレッドたちのように、地位があるわけでもないし力があるわけでもない。
魔族と交渉できるようなものを、なにひとつとしてもっていないのに。
それなのに、リュシーダサンイは望みを叶えてくれた。
危ないときは守ってくれたし、悲しいときはやさしく手を握っていてくれた。
一緒に、笑ってくれた。
「オレ……リューのために、なんにもしてないよ……リューはオレのために、いっぱい嬉しいことや楽しいことをしてくれたのに……オレと一緒にいてくれたのに。自分のことが嫌いだったオレを、好きだっていってくれたのに」
ケイは震える手をきつく握って、胸から溢れそうな感情を堪える。
自分はまだ、なにも支払っていない。
いや、返してはいない。
たくさんのものを与えてくれた大好きな友に、なにもしてあげてはいない。
そう。だから、ここにいるのではないか。
「……なにもできない、ではなくて、なにかしなきゃ。リューを悲しませるのは、嫌だ。マラシトのみんなが傷つくのは嫌だ。オレは守ってもらった。好きだって言ってもらった。だから、今度はオレが守らなきゃ」
相変わらず、両の瞳からは涙がこぼれるけれど。
「うさぎさん」
まっすぐに、漆黒の魔族に向き直った。
「オレにリューがどこにいるのか、教えて。対価は、ちゃんと払うから」
「ちょ、ちょっと待った、ケイちゃん! それは俺たちが!」
エゼルレッドが慌てた声を出す。それでも、ケイはそちらを見なかった。
ただまっすぐ、魔王の側近を見つめ、
「うさぎさんはオレになにしてほしい? オレはなにをしたら、うさぎさんに教えてもらえるの?」
「ケイちゃん!」
たぶん。
無茶なことをしている。
それは、なんとなくわかっているつもりだった。
魔法使いでもないというのに魔族と交渉するなど、危険で無謀なことなのだろう。
ミリードの魔導師たちを信頼していないわけでもない。信頼している、もちろん。
けれど、一刻もはやく魔王の居場所を知らなくてはならないのだ。
リュシーダサンイと別れてから、もう既に三時間も経っているのだから。
だから、
「オレはなにももっていないけれど、できることはするから!」
いつもは声を張り上げることなんて、ない。
生まれてはじめて、大きな声を上げた。
驚いたのだろう、いっそケイの口を押さえてしまおうかと伸ばされていたエゼルレッドの両手が、視界の端で宙に浮いたままになっている。
しん、と回廊が静まり返り、自分のなかで鳴る心臓の音だけがうるさく響いていた。
答えは。
魔王の側近の、答えは。
沈黙のなか、じっと息を詰めて待つ。
すると、
「ケイ・イーリィ」
ひどく滑らかな耳に心地よい低音で、漆黒の魔族がその名を呼んだ。
「アルネヴと一日遊べ」
「……え?」
「遊ぶなら、教えよう」
厳かにすら聞こえる声音と、知性を感じさせる泰然とした佇まいで、それとは釣り合わない子どもじみた条件を漆黒の魔族は寄越した。
「えっと……アルネヴ? うさぎさんのなまえ?」
こっくり、と頷く魔族の長い耳がおおきく揺れる。
「え、えーと……アルネヴと一日一緒に遊ぶだけでいいの? それで、リューがどこにいるのか教えてくれるの?」
こっくり、とふたたび魔族アルネヴがおおきく頷いた。
隣りで青い瞳の魔導師が驚きのあまり、えー、と抑揚なく茫然としたようにつぶやくくらいだ、それはおそらく彼らにしてみれば予想外も甚だしい対価なのだろう。だが魔法使いではないケイですら、アルネヴの答えには驚いた。どれほどに世間知らずであろうが、魔王の居場所を教えることと自分と一日遊ぶことが吊り合うとは、さすがに思えなかったのだ。命を寄越せ、とまではさすがに言われなかったとしても、こちらが差し出すことを躊躇うようなものだと思っていた。
「ほ、ほんとにそれでいいの? ちなみに何をして遊ぶの?」
「ケイが魔王といつもしていること」
「それでいいの?」
「それがいい」
深々と頷いたアルネヴに、ケイはちいさく苦笑する。しかしすぐに泣いたせいで赤くなった瞳を和ませ、わかった、と微笑み、
「じゃあ、リューとマラシトに帰ったら、一緒に遊ぼうね」
そう言うと、アルネヴは嬉しそうに長い耳をぐるぐると回した。
「それで、うさぎさん。あ……えっと、アルネヴ」
「うさぎさん、でいい」
「うん、ありがとう。それでね、うさぎさん。リューは、いまどこにいるの」
「海上」
「……え」
「海の上」
「…………えーと」
「海上を高速飛翔中。あと三分でブロキス帝国領アルティーア」
「び、びっくりしたぁ。びっくりしたぁ! 海上、って教えてくれるだけなのかと思ったぁ!」
ちょっと変な汗が出た、とケイが額の汗を拭うそばで、エゼルレッドが離れた場所で待機していた衛兵に既に指示を出している。そのようすを見やり、
「ルーくん」
声をかけると、眉を下げてくちびるを歪めた顔でエゼルレッドが肩越しに振り返った。
なにを頼まれるのか、予想がついているのだろう。
だからケイは、精一杯にっこり笑って言った。
「お願い、ルーくん。うさぎさんは連れていけないから、オレをアルティーアまで飛ばして」

音はない。
耳が痛くなるほどの静寂だ。
空は闇を内包する雲に覆われて尚、真紅に染まっていた。
時折、金色の閃光が稲妻のように駆ける。
何者も声を上げなかった。
上げることすら、できなかったのだ。
上空に突如現れた、恐怖に。
そこにある穢れを具現化した姿の、魔王に。
高圧の魔力は大地と空気を震わせ、そして惜しむことなく放出される威圧が肌を刺し貫き、いまにもなにもかもに、魂にすらも罅が入り、破砕されてそのまま消し飛ばされてしまうのではないかと否応なしに思わされた。
自分たちと魔族たちの血に濡れたまま、ただ、恐怖に声も出せず震え竦みながら、上空で巨大な翼を広げる黒を纏った魔族をブロキス帝国軍の精鋭たちは見上げている。
じっ、とこちらを無言で見下ろす冷酷かつ残忍に光る紅蓮の双眸から、目が離せないでいた。
誰かがわずかでも声を上げようものならば、誰かがわずかでも動こうものならば、その不気味な静寂は呆気なく破られるだろう。
怯える本能が、くちびるを封じ、全身を縛りつけていた。
そこへ、
「リュー!」
不意に、血塗れの大地に大輪の光の花が咲き、その中心から声が上がる。
動けない兵士たちの喉が、声のない悲鳴を上げた。そして、
「リュー、やめて!」
転がり出るように魔術の花からたったひとり飛び出してきた真白い子どもの姿に、ただただ瞠目する。
ケイは、走った。
そのたびに泥やそこに散った赤い色を服の裾や白い頬にまで跳ね上げるも、立ち止まることなく濁った黒に染まる魔王に向かって走りに走る。
その場に満ち溢れた目に見えない圧に、まともに息などできない。心臓も壊れそうなほどはやく鳴っているというのに、どんどん凍えていくようだ。
ひどい動悸と目眩に足が縺れそうになるが、それでも声を張り上げた。
「もうみんな戦えないよ! 怖がってるだけだよ! だからやめて! みんなを殺さないで! 下りてきてよ、リュー!」
瓦礫に足をとられて膝をつくと、そこが切れて血が溢れる。それでもくちびるを噛みしめ立ち上がり、血の臭いと煙とを吸い込んで痛む喉が張り裂けそうになるほど声を上げた。
「おねがいだから! みんなを殺しちゃったら、リューがからっぽになっちゃう!」
赤い空に、それは悲鳴のように響き渡る。
ひどく冷たい表情で黙ってこちらを見下ろす魔王を、地上に引き戻すために。
「リュー! オレのところにきて! リューが悲しいのは、オレ、嫌だよっ!」
ぐしゃり、とまたなにかにつまずいて転ぶ。
ぎこちなく振り返ると、骨が剥き出しになった人間の足が瓦礫の下から飛び出していた。そのわきに、獣毛に覆われた肉片が落ちている。
「ふ……っ……うぇ……っ」
悲しくて、辛くて、喉が詰まった。
拭っても拭っても、涙は溢れて流れ落ちる。
苦しくて、痛い。
目のまえに、思考に、闇の幕が下りはじめる。
今度は起き上がることすらできず、もがいた。
「リュー! お願いだから、下りてきて……っ!」
両手を赤いぬかるみに埋め、朦朧とする意識のもと、噛み合わない歯の隙間から必死に訴える。
身体の奥底が冷えて、どうしようもなく震えた。
泥を掴む指先も白さを増して、青白いほど。
「……リュー……」
水分の多い泥が耳もとで跳ね上がるのを聞いたが、それは弱々しい身体が限界をむかえたから。
ケイは指先ひとつ動かせぬままぬかるみに沈み、それでも、赤い空に留まりつづける魔王の姿を祈るように見つめた。
そのとき、
魔王が、咆哮した。
激しい怒りに震えるように、深い悲しみに慟哭するように。
いくつもの音程と長さを抱える不可思議な聲で、長く。
そして、その咆哮によってその場に注がれた魔力の圧に、火がついた。
ゴウ、と獣のように吼えて、金色の炎が沸き起こり、巻き上がる。
巨大な舌で舐めるように、悲鳴を上げて地面を這い逃げようとする兵士たちの上、人間と魔族の血で穢れた大地を、炎が駆けめぐった。
ばたばたと力尽きたように地に伏せる兵士たちの苦悶に満ち絶望に支配された顔を、ケイは金の炎に取り囲まれながら、じっと見つめていた。
そう、なぜか熱さを感じなかったのだ。
まるで幻のようにその炎には熱がなく、それどころか、ゆるりとその炎に頬をなでられるたびに、呼吸が楽になった。
よくよく見ると、倒れ伏した兵士たちにも息があるようだ。
「なぜここにいる」
不意に、冷たい声音が頭上に降ってきて視線を動かすと、恐ろしく醜い、おぞましい黒を纏った魔王がすぐそばにいた。
「……リュー?」
ひどく掠れた声を絞り出すと、魔王の眉にあたるだろう恐ろしい獣の顔面の一部が、ぴくり、と動いて顰められる。
「ごめん、ね」
そう言うと、さらに顰められたそこが引き絞られた。
「ごめんね、リュー。見られたくなんか、なかった、よね……」
「恐ろしいならば、恐ろしいと言え」
「うん、ごめん……怖い、よ。でも」
でも、リューだから。
そう言って、軋む身体を無理に動かし、泥から起き上がる。
「怖いけど、ね。でも……オレの大好きな、リューだから」
そっと、黒く塗り潰された飛膜と翼とに手を伸ばし、そのまま雪崩るように目のまえの魔王に抱きついた。
おそらく、ケイのなかに溢れた、怖い、という感情は魔王に流れ込んでいる。それでも、ケイは魔王の身体に細い腕をしっかりと巻きつけた。
怖いのは、リュシーダサンイではない。
この場に満ち溢れていただろう憎悪や殺意、狂気や恐怖というもの自体が、怖かった。
「オレ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ怒ってるんだからね」
「……怒っている?」
「まえに、オレに言ってくれたよね。おぞましいものを見てみるか、って。それでも構わない、って。それって穢れた自分も、オレに見せてくれるってことだったんじゃないの? それを、オレになら見せてもいいって思ってくれたってこと、だよね? それなのに、オレのこと、置いていったから……」
魔王の身体は、ひどく凍えている。
夜闇から生まれた魔族の身体はもともと熱くはないとはいえ、それでも抱きついた魔王の身体がいつもより一層冷たくて、それがとてつもなく悲しかった。
だから、慌てて首を振る。
「ううん、違う」
そう言って、黒い獣毛に顔を埋めた。
「違う……オレ、だよね。オレが弱いばかりに、リューはオレを遠ざけるしかなかった。弱いオレなんかに、見せたくなかったんだよね。ごめんね」
ごめんね、と繰り返すと、ふ、と空気が揺らいだ。
魔王が苦笑したのだ。
「ほんとうに弱い人間が、ひとりでこんな場所に乗り込んでくるものか」
ややあって呆れたような声音で、魔王が言う。
「おまえは弱くなどないぞ。出会ったときから、強かった」
「……え?」
「この俺が言うのだから、間違いはない。力はなくとも、おまえは確かに強かった。だから俺はおまえに、おまえを好きになって欲しかったのだ」
え、と顔を上げると、穢れが魔王の身体から剥離しはじめていた。
ばらばらと、羽根が抜け落ちるように、魔王を覆っているおぞましい黒い穢れが崩れていく。やがてその下から、乳色の肌が現れた。
「ほんとうに弱いものだったならば、おまえはとうに死んでいた」
くす、と穢れの下から現れた薄紅色のくちびるが綻んで、やさしい声音で魔王が言う。
「……ぁ」
突然腕に抱えていた身体の質量が変わり、それにつられるようにして傾ぐと、しなやかに力強い腕で逆に抱きとめられた。
頬に感じたやわらかさに思わず頬が赤くなったのは、金の光が踊る真紅の花を連ねたような髪が流れる、目のまえにある胸がまるく豊かに膨らんでいたからだ。
その魔王が、背から生やした猛々しい赤い皮膜と優美な黄金の羽毛に包まれた翼を、力強く一度だけ羽ばたかせた。
すると、
「あっ」
すべての穢れを飲み込んだ金の炎が、魔王の翼に巻き取られて上空に渦を巻くようにして駆け上がる。火の粉が星のように煌めく。
「ケイ。勘違いしないでね」
ふと、口調をやわらかくして魔王が言った。
「ケイは俺になにもしてないわけじゃないよ」
「え?」
「ケイは、ケイが望んでいるから俺がケイと一緒にいる、って思っているんだろうけれど。それだけじゃないよ。俺も、ね。俺もケイと一緒にいたいから、いるんだよ」
にっこり、と。
明るく笑んでみせるその顔は、いつものリュシーダサンイのもので。
「それで、いいんだよ」
そう、長い爪で傷つけてしまわないようにそっと頬を撫でられて、くしゃりと顔が歪んだ。けれど泣いてしまわないように、そのせいで言いたいことを言えないままになってしまわないように、ケイは必死で涙をこらえながらリュシーダサンイの真紅の瞳を見つめ上げる。
「オレ……なんにも考えずに、ただのんびり楽しく暮らしていけばいいって思ってた」
「うん」
「でも、オレがもっと強かったら、こんなことにはならなかった……よね。リューたちがどんなにやさしいか、どんなに素敵なのか、知っているのはオレだけなのに。なのに、オレがなにもしないで遊んでばかりいたから」
「ケイはまだ、子どもだった」
「でも、ずっと子どものままではいられないんだ。またおなじことが起こるかもしれないのに……オレ、またなにも出来ないなんて、絶対いやだ」
「なにもできなかったなんてことは、ない。ないよ、ケイ」
ほら。
そう言って、リュシーダサンイが天を仰ぎ、ケイもそれに倣った。
そして、ゆっくりと瞠目する。
「ケイ。力を溜めよう」
空は、いつのまにか夜闇に染まっていた。
深く暗い青に、無数の星々が瞬きを繰り返している。
そしてそこに、魔王の炎と翼によって打ち上げられた穢れが、金の凍えながら燃える炎によって浄化され白く輝き、まるで巨大な花のように集っていたのだ。
「俺は確かに……ケイに、穢れに塗れた醜い俺の姿を見せるのは、厭だった」
「……ごめんね」
「ケイが謝ることではない。俺が、俺の眷属や人の子たちが傷つけ合っている光景を見たケイの傷つく姿を、見たくなかっただけだ。穢れに塗れた俺が醜いことは自覚しているけれど……それでも、寄りかかれずにはいられないから。そんな弱々しい魔王を目の当たりにして、自分の魂や力を食わせてやろうなどと、いったいどの眷属が、人の子が思うか。だから、置いていった」
ふ、と形の良いくちびるが苦笑を吐く。そして、
「ごめんね、ケイ」
今度はリュシーダサンイが、そう言った。
ケイは豊かな胸に頬を埋めたまま、ううん、と首を振る。
視界の隅に映る天空では、巨大な白い花がゆっくりと崩れはじめていた。
「でも……じゃあ、オレ、来なかったほうがよかったのかなぁ」
「いや、来てくれて良かった。来てくれてありがとう、ケイ」
花火のように、花が弾ける。
弾けて、放射に天空を流れた。
ここで散った魂が、思いが、白く輝きながら星のように地上に降ってくる。
「ケイ、力を溜めよう」
ふたたびそう言って、リュシーダサンイは降り注ぐ白い輝きを受け止めた。
「オレ、リューたちを傷つけたりしないように、強くなる」
「うん。ごめんね」
「リューは、悪くないよ。誰も……悪くないよ」
「うん。でも、ごめんね。俺ももう、ケイを泣かせたりしないよ」
ごめんね、と。
星を浴びながら繰り返し言うリュシーダサンイの冷たい身体を、ケイは自分の熱を分け与えるように無言で強く抱き返した。
もっと強くなろう。
やさしい友のために。
そして、友が好きでいてくれる自分のために。
強いひとになろう。
そう、流れ落ちる星の群れに、ケイは誓った。



後日。
戦場にいた兵士たちから魔王とその眷属、そしてケイ・イーリィに連なる記憶とあたりさわりのない別の記憶をすり替えるということをやってのけたミリードの魔導師たちは、等価ではない、と突き放そうとしていた魔王リュシーダサンイより、ケイの口添えもあって、魔王によるミリード守護を辛くももぎとった。
尚、三人目の子どもの出産のため若い妻に付き添っていたオルブライト魔導師長は、うんざりするほどののろけを聞かせるついでに、結局ケイに会えなかった、と魔王の側近に散々泣きごとを聞かせたらしく、翌々日になって漆黒のアルネヴは長耳をよれよれにしてマラシトに帰還し、ケイとリュシーダサンイに三日がかりで慰められたという。

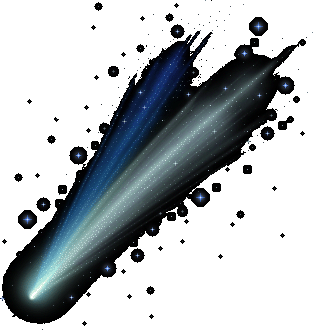
Fzユイロス様の竜稀様が、7777の地雷もといキリ番を踏んでくださいましたv
そして『鏡の国のアレとソレ』か『エンデ』の番外を、とリクしてくださったので、
『アレとソレ』に出てきてもらいましたw
ちょっとケイちゃんを泣かせすぎた気がしますが、それでもちょっとは成長したんじゃないかと……成長、したかな?
そして、なんと! 竜稀さんが『流星群』の挿絵を描いてくださったのです!
すごく素敵ッ! 嬉しい♪ ありがとうございましたv 2009.12.14
