
|
ナクターナルの森の月
|

|
「欲しいものが、ある」
そう言ったのは、人の子。
「言ってみろ」
そう答えたのは、人ならぬもの。
「世界」
短く言うことばは、真剣そのもの。
「は。人の子とは、随分と大それたことを言うものだな」
対する答えは、嗤っていた。
至高の宝玉ともいえる黄金が輻射に走る真紅の双眸で、じっと目のまえのちいさな存在を見据えて、冷ややかに。
そして、
「いいだろう。ちょうど暇をもてあましていたところだ。その望み、叶えてやろう」
世界は、気まぐれで。
どこまでも鮮やかだった。
 深くて暗い、森のなかだ。
闇の向こうから手招きするのは、甘く心を酔わせる芳香を放つ、花。
月の色に輝く花は、芳しき夜の女王の吐息と白き指に愛でられて艶やかなる花弁をしどけなく開き、甘い蜜を求めて舞い彷徨う羽虫を誘う。
大の男が両腕を回してもなお抱えきれないほどに育った大樹の幹に絡みつくのは、青々とした蔦と、色鮮やかな毒蛇。
つい、と何者かの気配を察した蛇は、その三角形の頭を擡(もた)げた直後、するり、と幹から引き離されて声のない悲鳴を放つ。
ぶちっ、と。
音を立ててその頭のすぐ下あたりを噛み切ったそれは、真っ赤に濡れたくちびるを、ぺろり、とちいさな舌で舐めた。
ちいさな、人影。
いや。それは、人、などではなかった。
漆黒の闇のなかにありながら、その双眸は黄金色と真紅に輝いている。
人の目には、森のなかは漆黒。
人の耳には、森のなかは静寂。
だが、それの黄金が輻射に走る真紅の双眸は、無作為に巻かれた真紅の髪から覗く先の尖った耳は、闇の真の姿を見聞きしている。
世界は、鮮やかだった。
世界は、濃厚だった。
「きょうは、賑やかだな」
それは、ごくん、と蛇を丸呑みにした喉をちいさく鳴らすと、誰に語りかけるでもなく、つぶやく。
男にしては艶やかな甘さを含んで、高い。
女にしては雄々しい深みを響かせ、低い。
そんな声音で、つぶやいた。
すると、ぽぅ、と傍らにふたつの蛍のように儚くまるい光が現れる。それはピクピク動く尖った耳のそばで、揺れた。
「……人の子?」
双眸が、軽く瞠られる。
そして鼻を動かし、空気の匂いを嗅ぐ。
「迷い込みでもしたか」
つぶやく声音に、笑みが滲んだ。
「ふうん。おまえは眷属たちに触れてまわれよ。手を出すな、とな」
行け、とまるい光に向かって命じるなり、それは大樹のつくりだす濃い影のなかへと入り、そのまま、溶けるように姿を消した。
その、しばらくあと。
人の子の手に長く触れられることなく、その記憶の隅で埃を纏う、神殿。
苔生した石造りの内側にさえ撒き散らされた花々の芳香の淀みが、通り過ぎる影に揺れる。乱れる。
奥の、さらに奥。天井の崩れ落ちた部分から覗く尖塔、それに掛かる細い月の落とす頼りない明りが、かろうじて届くというあたり。
そこに、常にはない人の子の姿があった。
連れはない。ただひとり、決して急がずゆるりとした、しかしそれでいて決然としたようすにさえ見える確かな意思を持った歩みで、神殿の最奥へと向かっている。
その姿は、あたかもあたりに乱れ咲く夜の花々のごとく。人のなかにあっては、なかなかに目に愉しい姿である。
歩むたびに揺れる癖のない髪は、輝く月の金色。
甘すぎることなく整った容貌は一瞬女かと判じかねるものではあったが、薄い皮膚が包んでいるのは見苦しくない程度に鍛えられたしなやかな若い男の身体だ。
昼の空の色をそのまま映したかのような双眸は、人にとっては底知れない闇と映るその場にあっても、ただまっすぐに前を見据えている。
そして。
男は、神殿最奥に鎮座する『それ』へと、無言で手を伸ばした。
花々が、風もないのにざわめいたことに気付かない。
そこかしこに落ちる濃い影が、不思議に揺れたことにも気付かない。
ひたり、と。
背後の闇に浮かぶ白い裸足が石床に触れたことにも、気付かない。
ただ目のまえにある『それ』を手に入れようと、軽く息を詰めた。
鋭い牙並ぶ獣の貌。
湾曲した水牛のようなかたちの角。
猛禽の爪を持つ、力強くもしなやかでなめらかな三対の人の腕。
羽毛に覆われた一対の雄大なる翼と、鉤爪を持った二対の荒々しき飛膜。
ひと抱えはあるだろう太さの三本の蛇のようにうねる、長い尾。
くっきりと大きく切れる、双眸。
それらが見事なまでの左右対称をもって、禍々しくこちらを見据えていた。
深い闇の艶を放つ漆黒の石像が模すものは、
魔王。
それは闇を統べる、禍々しき神聖。
世界を舐める、凍りながら燃える炎。
神殿は、光と闇に彩られた世界の半分を支配する王のためのものであった。
魔王像は、人の子の闇への恐れと畏れを映し表したもの。
男は知らず、身体を震わせた。そしてふとそれに気付き、舌打ちをする。
緊張か、それとも畏怖であるのか。手指が思うように進まない。
目のまえにあるものは、ただの石像。
人の子の記憶の森に置き去りにされて、ずいぶんと久しい石の塊。
そうであるにも関わらず粟立つ肌が、厭わしい。
することはいつもとなんら変わりない。目のまえの石像の首にぶら下がる『それ』を、金と柘榴石でつくられた『魔王の首飾り』をこの手にいただくだけ。
伸ばした手指を一度戻し、男は息を吐きだした。そしてふたたび、空色の双眸で見据えたそれに意を決して手指を伸ばし、
「おい、人の子」
背後からかかった声に、全身が凍りついた。
それは男にしてみれば、唐突。
男が黙してさえいればそこにはありえないはずの、音だった。
とっさに隠し持っていた刃物を懐から抜き、振り返る。するとそこに、
「今宵は賑やかだ」
禍々しくも美しい女が、立っていた。
生まれたての真珠のように輝くなめらかな肌に包まれた、若くまろやかな姿態。
王宮にある紅玉から紡いだかのような艶やかな髪が、剥き出しの白い肩に八重咲きの花が連なるようにして流れ落ちている。
頬に影を落とす長い羽根扇のような睫毛に覆われた双眸は、渦を巻いては輻射に走る黄金を孕んだ真紅。
「そうは思わないか?」
ふっくらとした蠱惑的なくちびるからこぼれる声音は、低すぎず高すぎない耳に心地よい甘さを含んでそう問いかけてくる。
豊かに張り出した乳房と細くくびれた腰とを見せつけるように、ひたり、と女は妖しく歩み寄った。
女の纏う、裾にちいさな鏡がいくつもつけられた肌を透かせる薄布が、翻る。
魂が食い破られるのではないかと恐怖すら覚えるほどの、美貌だった。
危険だ、と。
本能が、それを告げていた。
そう。目のまえにいるものは、捕食するもの。
とっさに後ずさったが、背に冷たく硬い石の感触を覚えて顔を歪める。
「おまえ……誰だ」
追い詰められたものの悪足掻きか、とおのれを嗤ってはみるものの、このままおとなしくしているのも柄ではなかった。
捕食者の余裕と婀娜なる威圧とを見せる目のまえの女を、きつく睨み据える。
そうしながらも、この場を切り抜ける策がないものかと頭のなかを探った。
しかし、
「逃がすと思うのか? この俺が」
くつくつ、と女が喉を鳴らして笑う。
「ついでだから教えておいてやる。おまえの持つその得物は、俺には効かない。ただの人の子の刃物が、俺の身体を貫くことはない」
青白いほどに白い手指の先で刃物を持つ手指を撫でられて、くちびるを噛みしめる。
ゆっくりと、男の空色の双眸に金の花が甘い花弁を開いた。
自己防衛のための、魅了の揺らめき。
それは男の、生まれ持った力。
しかし、
「そして、この瞳の力が俺を捕えることも、ない」
するり、と。
目蓋の上を撫でられて、臓腑に氷の手を差し込まれたかのような錯覚が襲うと同時に、その唐突な冷気によって魅了の花が萎えてしまう。
隠し持った武器も、瞳に秘めた力すら効かないという。
それどころか、語ってみせたわけではないそれを、すべて見通されている。
「人ではない、な」
疑問ではなく、それは確信。
音にしたそれは他人に聞かせるにはあまりにも情けないものではあったが、いまさらどうすることもできない。
そして、女は赤いくちびるを凄絶な笑みに吊り上げた。
「ああ、そうとも。俺は人の子ではない」
人ではない、とあっさりと認めた女の白い腕が、蛇のようにするりと首を抱きにくる。
「寄るな」
「ふふ。寄らねば食えんだろう」
「やめ、ろ……っ!」
逃れようと身体を捩ると、背後の魔王像に寄りかかるような格好になった。
ぬ、と身震いするほどに醜いその貌がこちらを食い破ろうとするように、左の肩に現れる。同時に、目が眩むような女の美しい貌が、右の肩にすり寄った。
そして、鈴を転がすかのような笑みをこぼし、
「俺はリュシーダサンイ」
耳朶に息を吹きかけるように、女が名乗る。
とたん、膝から力が抜けた。
「人の子。おまえの名も、寄越せ」
ぐらり、と身体が揺れ、世界が反転する。
「……ぁ……アル、ト……」
食われるのか、と生命の終わりを感じた瞬間、男はその耳に、まっすぐに自分を呼ぶ声を聞いた気がしたのだった。
そして。
「だいたい、こんな紛い物を盗んでどうするつもりだ」
不意の息苦しさを感じて飛び起きると、すぐ傍らに豪快な胡坐をかいた人ならぬ美貌の女がいた。そしてその、小首を傾げた女の白い手指が、なにかをつまむような形のまま、宙に浮いている。
どうやら、気を失っていたところに、鼻をつままれたらしい。息苦しいはずだ。
いやそれよりも、とアルトは上半身を完全に起こすと女から距離をとるようにずれて、自身の身体を見まわした。
両手に、両足、欠けていると思われる個所も、痛みを感じる箇所もない。
すると、
「あぁ、急に動くなよ。人の子はか弱いから、すぐに眩暈を起こす。それに、心配せずとも食ってないぞ、そんなに」
そんなに、と不穏な言いようをして、胡坐の左膝に肘をつきほっそりとした顎を支える女は、しかし、先ほどのような禍々しさを消したどこか人懐こさも感じる表情でくすくす笑った。
「なんだ、それは。いったいどういう意味だ」
「言葉通りの意味だ」
わけがわからない、と眉を寄せながらじっとアルトが白い顔を見つめると、女は笑みをひっこめて頬杖を外し、すい、と背筋を伸ばす。
とたんに、ぴり、と全身に緊張が走った。
「それで?」
「な、に」
「それで、こんな紛い物を盗んでどうするつもりだったのだ」
おなじ問いを、繰り返される。
その手には魔王像の首に下がっていた、飾り。
「おまえ、盗人だろう。紛い物と本物の区別もつかなかったのか? こんなものを売っても金にはならん」
首飾りは、中央に赤い玉が填められた金色の板と、そこから下がる細長い鎖の先についた獣の爪のような形をした赤い石でできている。
凝った意匠ではあるが、やはり女が言うように本物の宝玉の輝きは、そこにない。
どうみても紛い物のそれに、しかしアルトは強い視線を当てた。
「べつに……それが硝子玉だろうが、そんなことは関係ない。おまえに教えてやる義理もない」
「ふうん。まあ、いい。欲しいならばくれてやる」
ほら、と自分のものでもないだろうに、女は首飾りを無造作に放り投げる。
片手でそれを受け取ったアルトは、まじまじと手のなかのものを見た。
「どうした。欲しかったのだろう? もっと嬉しそうな顔をしたらどうだ。それとも……そんな紛い物ではやはりおのれの願いは叶わないと、ようやく気付いたか」
はっ、と顔を上げると、すべてを見通すようかのような瞳に出会う。
魂が吸い寄せられるのではないかと思わずにはいられない、それこそがほんものの宝玉であるかのような、双眸。
知らず、アルトは喉に息を飲んだ。
「それは……」
口ごもると、くつくつと女が笑う。そして、ゆっくりとした動作で薄布を揺らしつつ立ち上がり、こちらを冷えた眼差しで見下ろした。
「紛い物で叶うような、願いか?」
「違う!」
短く叫んだ瞬間、しん、とあたりが沈黙する。
苔のなかで鳴いていた虫の声も、月に歌う夜鳥の声もぴたりと止んだ。
天井の隙間を、雲が流れる。
濃くなる、花の香。そして、闇。
心臓が、震える。拍動の、そのあまりの速さに身体がおおきく揺すぶられるようだ。
「ふふ。それならば言ってみろ」
「なに」
「聞くだけならば聞いてやる。叶えてやるかどうかは、また別だが」
「おまえ、いったい……」
「聞いていなかったのか。おまえのその耳は飾りか? いいか、もう一度だけ教えてやる。俺の名はリュシーダサンイ。覚えたか?」
「リュシーダ……サンイ……?」
つい、と真白く優美な手指が、背後に向けられた。
つられるように肩越しに振り返ると、そこには禍々しいかたちの石像。
「なあ、アルト」
甘くありながらどこか冷たい響きを内包する声音に呼ばれてふたたび顔を女に向けると、金が踊る真紅の双眸がゆるりと細められる。
「紛い物では叶わない願いとやらを聞かせろ。俺を退屈させるな」
ざわり、とそこかしこから湧き上がる冷気に、足首を掴まれた。
そして瞬く間に、それは全身を駆ける。
「おまえ……まさ、か」
石像を指していた指が、つい、と女の首にひっかかっていた金の鎖に絡められた。そして、
「っ!」
しゃら、と。
指先に引かれて、美しい音色を奏でながら女の肩を滑り、その豊かな胸元に落ちたのが、
柘榴石と金でつくられた、首飾り。
鎖の先でゆらゆらと揺れる獣の爪のかたちをした紅玉は、鳩の血色に輝いている。
ほんものの首飾り。
ほんものである、『証』。
「嬉しいだろう? おまえの目のまえにいる俺は、紛い物ではない」
「魔王……っ!」
 世界が欲しい、と願った。
紛い物などで叶うはずはない、と。
そう、思ってはいた。わかっていた。
けれど、試してみたいと思ったのは、どうしようもない焦りで、焦がれだったのかも知れない。
ほんものだと明かされて、しくじったと思うと同時に、期待した。
手のなかで、紛い物の首飾りが音を立てる。
「随分と大それたことを言うものだ」
つ、と背を冷たい汗が流れた。
「それで? おまえのいう世界とは、なんだ」
こちらが答えるまえからその答えを知っているのだろう宝玉の瞳が、闇のなか、炯々と冷やかに見据えてくる。
その魂までもが震える恐ろしいほどの威圧感に、しかし、それでも逃げだしたくはなくて、まっすぐに見返した。
「人の子とは斯くも浅ましく愚かなものか」
凍りながら燃える炎の気を纏う闇の王は、くつくつと嗤う。
「たかが小娘ひとりのために」
「おまえにとってそうだとしても」
「いいだろう」
不意に思ってもみない言葉を聞き、え、と思わず眉を寄せて訊き返すと、
「ちょうど暇をもてあましていたところだ」
「な、に」
「叶えてやるぞ、その願い」
女は、魔王は。
赤いくちびるを笑みに吊り上げ、凝った闇を踏みしめるように一歩、歩み寄った。
アルトは指先ひとつ動かせないままに、それを見つめる。
耳もとで、闇が鳴る。
胸のなかで、激しく警鐘が響く。
「ただし」
来た、と頭の隅で思った。
どくん、と心臓が強く打ち、わずかの間忘れる、呼吸。
「対価を払ってもらう」
「俺の、精気を食らっただろう。他に、なにを」
言った途端、すい、と魔王の双眸が細められる。
「偉そうな口をきくなよ、人の子」
地を這うように低く響く声音に、世界が揺れたような錯覚を覚えた。
「確かにおまえの精気はわずかに齧った。だが、おまえのその手にあるものはなんだ。俺はそれをくれてやったぞ。いいか。払うべき対価は、等価。そして言ったな、人の子。紛い物では叶えられない願いだ、と」
「……っ」
「欲しいものを得るために対価を払う。それは世界の理(ことわり)のひとつ。理を学ぶ魔法使いですらないおまえが、賢(さか)しくこの俺と交渉しようなどとは思うな。欲しいならば、払え。払えないのならば、欲するな。覚悟がないなら願うな、人の子」
「覚悟がないわけじゃないっ!」
「ならばなにを差し出す。おまえの世界を手に入れるために、おまえはなにを支払う」
「俺は」
「『魅了の瞳』」
「……な、に」
「そのふたつの瞳を刳(く)り貫いて寄越すか」
いまさら『魅了』の力を得ずとも充分であろうはずだというのに、魔王は言った。
じっ、と。
細めたままの双眸でこちらを見つめたまま。
それがどこかやさしげに思えたのは、気のせいか。
「そうなれば、日々変化する鮮やかな世界の姿を、おまえは見ることができなくなる。だが、そのほかのすべてで、濃厚な世界を感じることになるだろう」
あの子は、やさしい。
だから、この瞳がたとえ『嫌いな瞳』なのだとしても、失ったならば泣いてくれることだろう。傍についてくれるだろう。
「どうする」
問われて、拳を握り締めた。
だが。
同情は、いらない。
欲しいものは、そんなものではない。
「寄越すのか、寄越さないのか」
けれど。
思い出してくれるかも知れない。
思い出して、欲しい。
その時、くす、と魔王の麗しいくちびるから笑みがこぼれた。
なんだ、と思うそのまえで、艶めかしい女の輪郭が揺らぐ。
影が、崩れる。
そして、
「アルトさん!」
濃い闇に包まれた神殿のなか突如響いたまっすぐな声に、呼ばれた。
驚いて振り返ると、闇の向こうにはじける陽の光のような明るい姿を見つける。
まだ幼さの残る愛らしい顔いっぱいに笑顔の花を咲かせ、こちらに向かっておおきく手を振って。
「アルトさん、こんなところにいたんですか! 探しましたよ!」
そこかしこにあった暗い影を、蠢く闇を、駆け寄るその小柄な少女が光に溶かすようだった。
世界が、それだけで色に溢れるようだった。
「ミコナ……?」
なぜここに、とアルトが瞠目すると、すぐ目のまえまできた少女はことりと首を傾げ、
「どうかしましたか」
常緑樹のやさしげな緑をしたおおきな瞳で、不思議そうに見上げてくる。
「だから、なんでおまえがここにいるんだ」
「なんで、って……だから、アルトさんを探しに。こんなところでどうしたんですか、心配したんですよ?」
やわらかそうな頬を膨らませて言うミコナに、アルトは内心でうろたえた。
さっ、と視線を走らせ、魔王の姿を探す。
願いは。
叶えられたのか、と。
しかし、それにしてはおかしい。目が見える。力のみを喰らわれたのかとも思ったが、どうやらそういうわけでもないらしかった。
「ここ、なんだか不思議なところですね」
暗闇を恐れるようすはまるでなく、むしろ面白いものを見るように瞳を輝かせて周囲を見回したミコナの声に、アルトは意識を引き戻される。
「ところでアルトさん」
「なんだよ」
「誰とお話ししてたんですか」
ひょい、と背中を覗き込むようにされて、慌てた。
魔王などに、この少女を会わせられない。
少女は無垢だ。危険なものを危険とも思わず、挙句、騙されて喰らわれてしまうかも知れない。
そう思ったのだ。
だというのに。
「リューとお話ししてたんですぅ」
「……は?」
またしても聞こえた不意の幼い声音に、アルトは一瞬頭のなかが白くなった。
「リュー?」
ミコナの傾げた首の角度が深くなる。
「オレのことだぞ?」
ちいさく上着の裾を掴まれ、視界が揺れた。
直後、ひょい、と先ほどのミコナとおなじ動きで、ちいさな影がアルトの背につくられた闇のなかから顔を出す。すると、
「わぁ! かわいい!」
ミコナが歓声を上げた。
驚いたアルトが視線を下げるとそこに、さきほどの女をずっと幼くしたような子どもがいた。
子どもは、つい、とその白い顔を上げてこちらを見るなり、愛らしい容貌にはあまりに不似合いな妖艶な笑みを浮かべて見せた。
くるくると金の光が踊る、紅玉の瞳。
「魔……っ!」
魔王、と声に出すところを寸でのところで止めて、アルトは絶句。
その脇で、ミコナは幼児の姿に縮んだ魔王の視線に合わせて腰を落とし、しきりにその赤い髪を撫でている。
「わぁ、わぁ、かわいい! アルトさん、ずるい! こんなかわいいおともだちがいたなんて。どうして教えてくれないんですか」
「どうして教えてくれないんですかぁ」
魔王は、ミコナを真似て白い頬をぷうっと膨らませた。
「心の狭い男は嫌われるぞぉ」
「……おまえ……っ」
「男はどどーんとでっかくなくてはならんぞ? なあ、ミコネス?」
「そうですよね! って、あれ? あれ? どうしてわたしのなまえ、知ってるの?」
「でっかいどー!」
「ほえっ? でっかいどー!」
ばんざい、と両手を高々と上げる子どもにつられて、ミコナまでもが両手を上げる。
その様に、アルトは軽い頭痛を覚えた。
「あれ? でも、アルトさん」
「なんだよ」
「だめじゃないですか。子どもは早く寝なきゃだめなんですよ! こんな遅くに、こんな暗いところで遊ぶなんて。ね。リューちゃん。おうちはどこ? もう帰らないと、おうちのひとが心配するよ?」
緑がかったやわらかな灰色の髪を揺らし、めっ、とミコナは子どもに向かってお説教だ。
「子どもに子どもとか言われたくないと思うぞ、そいつは」
なんと言っても、相手は魔王だ。
おそらくは自分たちよりもずっと長く生きている。
「もうっ! アルトさんの意地悪!」
「意地悪ぅ」
そう言いつつ、自分こそが意地の悪い笑みを浮かべる魔王を、蹴ってやりたくなった。
だが、そこは我慢だ。ここでほんとうに蹴ってしまっては、仕返しになにをされるかわかったものではない。それに、端から見れば、それはただの弱い者いじめ。ミコナが嫌うものだ。
アルトは深々と溜息をついた。
すると、
「さてと」
と魔王がぴょんと石床を蹴り、仔兎のように跳ねる。そして、跳ねた先でくるりと宙で一回転をした。
「オレはそろそろ行くぞ。おまえたちもさっさと帰るんだな。子どもは寝る時間なのだろう?」
皮肉な言葉とともに、ひたり、と裸の足は闇を踏み、無作為に巻かれた赤い髪が流れる。
幼く平たい胸に、重たげな首飾りが揺れた。
「おい!」
とっさにアルトが声をかけると、魔王はちいさな肩越しに振り返り、
「悪いな、人の子。俺は気が変わりやすいんだ。だが……盗人のおまえに教えておいてやる。対価さえ払えば、欲しいものは手に入る。精々、おのれを磨け。努力をしろ」
そうして、手に入れてみせろ。
そう、男なのか女なのか、子どもなのか大人なのかわからない、幾重にも響く不思議な声音で、そう告げた。
「それが、世界の理というものだ」
くす、と笑うちいさな、けれどどこかおおきな姿が、闇に溶ける。
「あ! 待って! ひとりだと危ないよっ!」
「おまえのほうが危ない」
慌てて後を追おうとしたミコナの細い腕を、アルトは引き止めた。
「え、でも!」
「だいじょうぶだ。その……家が、すぐそばにあるらしいから」
「そうなんですか?」
というか、ここは奴の神殿だ。
心のなかでそう呟いて、アルトはちいさく溜息を落とした。そして、ふとミコナが自分の右手を見ていることに気づく。
「アルトさん、それ」
手のなかには、偽物の首飾り。
「え。ああ。これは……もらった」
「ほんとうに?」
「なんで疑うんだよ」
「べつに疑ってるわけじゃないんですけど」
それでもじっと深い緑色の双眸で見上げられて、居心地が悪くなると同時に、
疑われるのは日頃の行いのせいだろう?
そう、背後の石像が笑ったような、そんな気がして、むっとした。
いいだろう、魔王。
いまに見ていろよ。
雲の合間から顔をのぞかせた細い月に向かって、アルトは不敵に笑ってみせ、そっと、赤い影を落とす月の光を吸った硝子玉を、ゆっくりと手のひらのなかに握り込んだ。
甘い花の香り。
賑やかな虫の声。
獣は月に吠え、鳥は星に歌う。
目眩がするほどに、世界は鮮やか。
気が遠くなるほどに、世界は濃厚。
けれど、人の子の瞳にとっては深くて暗い、静かな闇のなか。
気まぐれな王は、ひどく楽しげに笑った。
「きょうは、ずいぶんと賑やかだ」
 『鏡の国のアレとソレ』 目次 『鏡の国のアレとソレ』 目次 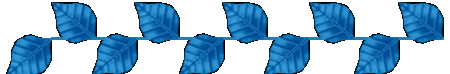
|