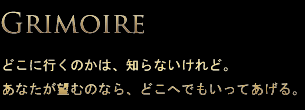
|
雪のうた
 散乱するゴミと派手なネオンの海に埋もれ、罵声と啜り泣きが響く町。
年中空を塞ぐ雲のせいで陽光から見放された、蜥蜴籠街(リザードケージ)。
その町唯一のフィオナ聖教会にほど近い路地にある、カフェだ。
冷たいコンクリートに囲まれた半地下の薄暗いそこで出会ったのは、『J』と呼ばれる腕利きの稼ぎ屋だった。
稼ぎ屋Jに会うのは初めてだ。
だが『彼』に会うのは、約五年ぶりだった。
「元気そうで何よりです、『ジュード』」
教会で与えられたその名で呼ぶと、さきほどからそっぽを向いている彼の、男にしては色白く滑らかであるらしい頬が、ぴくり、と引き攣るように動く。
それを見て、顔には穏やかな笑みを貼り付けつつ、髪にちらほらと白いものが混じっている若い司祭は、ある種の愉悦を腹のなかで噛み締めていた。
寝癖であるのかその一部が軽く跳ね上がった黄みの薄い金髪に、こちらをなかなか見ようとしないオリーブ色の双眸。
線の細い端正な容貌は、この灰色の町で稼ぎ屋稼業などをしているとはすぐには信じられないようなものだったが、しかし実際、Jの腰には使い込まれた銃が収まったホルスターが吊られている。
「こうしてまたあなたに会うことができるなんて……嬉しいですが、少々くすぐったいですね。まるで初恋の相手にでも再会したかのようですよ」
心にもない、しかも、相手が確実に嫌がるとわかっている言葉を、司祭は口にした。
すると予想通り、Jが心底嫌そうに顔を歪めつつ椅子をずらし、こちらとの距離をとる。
おもしろいなぁ、とは口には出さずに、司祭は白い法服の袖を揺らしつつカップを手にとると、意地の悪い笑みを浮かべそうになるくちびるをごまかすために不味いコーヒーを啜った。
「それで? 俺に頼みたい仕事っていうのは、なんだ」
「なんですか。久しぶりに会えたというのに、もう仕事の話……『兄』は悲しいです」
よよ、と司祭がわざとらしく目元を白い袖で覆うと、さっさと帰りたい、とでも言うようにJはカフェの出口である階段へと瞳をやる。
そう、稼ぎ屋Jは教会に拾われた。
いまからちょうど、十年まえだろうか。
その日もきょうのように、
雪が、降っていた。
陰鬱な空を見上げると、どこか楽しげに螺旋を描くように雪が舞い降りてくる。
頬に落ちたそれは、じわりと融け広がってこちらの頬を冷やす。
このまま。
こうしてじっとしていれば、この身体も凍えて融け落ちるだろうか。
足もとは、ぬかるみ。
そこに落ちれば、儚い雪はあっという間に汚れた色に消える。
世界は、ぬかるみ。
そこに生まれ落ちれば、儚い命はあっという間に汚れた色に消える。
この雪に、いったいなんの意味があるのだろう。
目に見えない塵を抱えて生まれた雪に、どれほどの価値があるというのだろう。
「フェリックス。行きますよ」
返事をするのが億劫だった。
代わりにそっと目蓋を閉じ、『フェリックス』と教会に名づけられた少年は深々と息をつく。
ぐい、と雪に濡れた冷たい頬をコートの袖で拭い、先を行く白い法服を熱のない灰色の、この街の空と同じ色の眼差しで眺めた。
ぬかるみを歩みだすと、泥と雪だったものがかき混ぜられてぐちゃりと音がする。
いつもどこにいてなにをしていても、虚しかった。
心が死んでいるのだから、身体が生きていてもしかたがない。
だからといって身体を殺そうと思うほどの力も、なかった。
ただ、虚しく死にながら生きているだけ。
確かに、薄暗い袋小路に売られるところを命からがら逃げ出し、そこを教会に拾われたが、それでも救われたとは思わなかった。
この町の一部の人間が苦しい現実から逃れたい一心で縋る女神に祈ったところで、虚しさが晴れることはない。
それでも拾われて三年近く経ってもそこにいるのは、叩き売られる先だったはずの人を散々に踏みつけにしては使い潰す袋小路に比べれば、いくぶんかマシだからというだけ。掃除をし女神に祈っておりこうにさえしていれば、寝床と食事は確保できる。身体を生かすだけなら、ほかよりもずっと楽にそれらを手に入れられるからだ。
フェリックスは、抱えた紙袋からこぼれ落ちそうな缶詰を、ぐっ、と無言で押し戻す。
魚の缶詰は、嫌いだ。
まるで小汚い猫のように、こればかりを食べさせられていたからだ。挙句、缶詰を買ってやるのも面倒になった親は、小金に目が眩んで人買いに子どもを売った。
だがそれも、この町ではよくある話だ。
そのときだった。
ふと、暗い路地に目がいったのは。
その路地に用はない。足を向ける必要もないところだ。
だというのに、なにがあるというのか、足が止まった。
なにか、いる。
いや。いてもおかしくはない。どこにも行くあてがなく、金もなく、襤褸に包まって路上に蹲る者などいくらでもいるのだ。
だが足が止まった。
目が、暗闇の向こうに吸い寄せられる。
「どうしました、フェリックス」
ずいぶん先を行っていた司祭が振り返るが、答えなかった。
ちら、となにか白いものが暗闇のなかで動いたからだ。
「そっちはいけませんよ。危ないから……フェリックス!」
制止も聞かず、フェリックスは路地へと入った。
転がっていた空き缶に爪先があたり、狭いその場所に甲高い音が反響する。
すると、
「……っ」
闇の向こうで、なにかが息を詰める気配がした。
「誰かいるの」
虚しさを抱えるフェリックスにとって、暗がりは恐怖でもなんでもない。
突然酷い目を見ることもじゅうぶんあり得るが、そんなことすらどうでもよかった。
けれど進んだ先にいたのは、酔っ払いでもなければナイフをもったごろつきでもなく、襤褸を被った路上生活者ですらなかった。
やがて闇に慣れた目がぼんやりととらえた姿に、思わず絶句する。
それは、白かった。
司祭の法服のような目にしみる白ではない。
もっとやわらかそうで、けれどどこか痛々しい白だった。
いや、実際、痛々しいものだったのだ。
「怪我、してる」
違う。それどころではない。
わかっていたが、フェリックスはなかば呆然とそれを見下ろしていた。
自分を路地の入り口から呼ぶ声を背後に聞くが、聞こえないふりをする。
なぜなら、目のまえの子どもは。
目のまえに膝を抱えてうずくまる子どもは、この寒空の下だというのになにも身に纏わず、ただ闇に白く浮かび上がる肌を晒していたのだ。
見たところ、十歳前後というところか。
ひとりで生きて行く力など、もちろんない。このまま放っておくと、確実に凍え死ぬだろう。
それでもフェリックスは、どうしようか、と逡巡した。
そのとき、寒さのせいであるのか肌に抱えたいくつもの傷と痣のせいであるのか、こどもが動きも鈍くこちらを見上げる。
その瞳がオリーブ色だった。
表情のない、けれどまっさらな。
なぜ。
ふと浮いたのは、疑問だった。
なぜ、そんな格好でこんな場所に放り出されているのに。
なぜ、そんなに傷と痣を抱えているのに。
つぎの瞬間、フェリックスは迷いなく着ていたコートを脱いだ。そしてそれを、震える子どもの肩に掛ける。
子どもは不意のぬくもりにちいさく震えはしたが無言でそれを受けると、視線を自分の泥に汚れた足先に落とした。
引き結んだくちびるは、色を失って青い。
凍えて声も出ないのだろう。
「えっと……女の子? それとも、男の子?」
顔立ちは愛らしいが、よくわからない。だが、訊ねる以外にも確認のしようはある。コートを羽織っただけのいまなら、それも簡単だろう。とはいえ、相手は犬や猫ではないのでそれもためらわれた。女の子だったなら、殴られても文句はいえない。
せめて答えてくれたならいいのだが、あいにく子どもは黙ったままだ。
どうしようか、とふたたび考えていると、
「フェリックス。なにをしているのですか」
ぐい、と仕方なく追ってきた司祭に腕を掴まれる。
「おや……子ども、ですか」
その声音には、少々呆れたような響きがあった。
おそらくは、フェリックスが他人に興味を持ったことが珍しかったのだろう。
「フェリックス。帰りますよ」
しかし、司祭に子どもを拾って帰る気はないらしい。
教会にはすでに、年長のフェリックスを含めて三人子どもがいるのだ。教会も金が余っているわけではない。それに、つい先日拾って間もない双子の赤ん坊ハリーとイザベルが死んだばかりだ。そんな気分でもないのだろう。
けれど、
「フェリックス!」
気が付くと、子どもの細すぎるほど細い腕を取っていた。
ずり落ちそうになるコートを掛け直しつつ、子どもを立たせる。
バサリ、とその膝の上からなにかが、紙の束のような音を立てて落ちるが、それがなんであったのかはすぐに闇に紛れてわからなくなった。
「フェリックス。どうするのですか、その……男の子を」
「……あぁ、えーと。連れて帰ります。僕が面倒をみますから、いいですよね?」
理由なんて、ない。
どうしてなのかもわからなかった。
それはあとになっても、おなじ。わからなかった。
けれど、この子どもを連れて帰ろう、とそのときフェリックスは思ったのだ。
蜥蜴籠街唯一のこの教会では、拾った子どもをAから順番になまえを与えている。
Fの頭文字を持つフェリックスは、六番めの子ども。
そして、そのフェリックスが連れ帰った新しい十人目の『兄弟』は、十番めの文字を頭文字に『ジュード』と名づけられた。
紹介するなり、もともと世話好きであるギルバートと自分にもやっと『弟』ができたと喜ぶちいさいドロシーが、ジュードにまとわりつく。
「ねぇ、どろだらけだわ。どうしたの?」
歳の近いドロシーが、黙ったままのジュードの頬を指先でつついた。
「身体を洗わないと、傷が膿んでしまいますね」
「あたしがおふろにいれてあげる!」
恩ある司祭の口調を真似るギルバートの言葉に、はいっ、と跳ねるようにして元気良く手を上げるドロシー。
それでも、ジュードは黙ってどこかぼんやりと床の木目に目線を落としているだけだ。
相当酷い目にあったのかも知れない。
フェリックスはそっと溜息をつきながら、ジュードのちいさな手を引いた。
「あー! まって、あたしもいく!」
「駄目だ。おまえは女の子だろ」
「いいじゃない、べつにぃ。あたしもジュードのおせわしたい」
「だったら、着替えを用意しておいて」
「おきがえ? どんなの?」
「とりあえず、ドロシーのものでいいと思う。大きさがおなじくらいだから。でも、ひらひらしたのは駄目」
「うん、わかった!」
そうして、ジュードの身体にこびりついた血と泥とを洗い流し、傷の手当をして戻ってくると、待っていたのが、
「……どこで見付けてきたんだ……?」
フェリックスも思わず呆然とつぶやくような、派手なピンクのワンピースと、なぜか三角の耳と長くて細い尻尾と思わしきものがついた黒いつなぎ。いや、きぐるみ。
「どっちがいいかなぁ」
嬉しそうに、ドロシーが右手と左手を交互に見やる。
「……こっちでいいんじゃないか?」
確かに、どちらもひらひらはしていない。
でもさすがにピンクはないだろう、と猫であるらしいきぐるみを指差した。
いや。むしろ、これを着た人間が見てみたい。それを見て笑うつもりはないが、どんなふうになるのか単純に興味がある。
そう思っていたのだが。
表情なくぼんやりと足を投げ出して座る黒猫を見たドロシーが、ぎゅう、とジュードの細い身体に抱きついて、頭を撫でまわし、
「わぁ、かわいいにゃんこぉ。ねぇ、ほらギル! すっごくかわいいよぉ?」
と、はしゃいでにぎやかな笑い声を上げた、そのとき、
「ん?」
はじめてジュードの表情が動いた。
迷惑そうに、軽く眉根を寄せたのだ。加えて、徐々に白い頬に赤みが差し、耳までもが赤くなる。
「あらぁ? ねえ、ほっぺがあかくなったわ。おこったの? それともはずかしいの?」
調子に乗ったドロシーが、ちいさな指でジュードのやわらかな頬を軽くつついた。
すると、さらに眉が寄りくちびるが歪んで、なんとなく泣き出しそうな顔になる。
それを見たとたん、
「……ぷ」
フェリックスは、ちいさく噴き出していた。
ギルバートとドロシーが驚いた顔をしてこちらを見たが、笑いは一度こぼれたら次々に込み上げてきてとまらない。
そんな顔をするくらいなら、手を振り払うくらいすればいいのに。
なんで我慢してるんだろう。
猫の耳と尻尾がついているのに。
本物の子猫だって、それくらいのことはするのに。
そう思ったら、おかしくて。
勝手に手が、耳のついたフードからこぼれるジュードのまだすこし濡れている金髪を撫でていた。
どうしてだかなんて、わからない。
けれど腹のなかが、くすぐったくて。
驚いたような、まんまるに見開かれたオリーブ色の双眸に出会う。
その、きょとんとした表情もなんだかおかしくて。
フェリックスは、笑った。
それだけのことで、ようやく全身に血が通ったようで。
ゆっくり屈み込み両手でちいさな手を包み込むと、ひどく、温かくて。
柄にもないけれど。
どうしようもなく、泣きたい気持ちになった。
「あのな。痛かったら、痛い。悲しかったら、悲しい。やめてほしかったら、やめて、ってちゃんと言わなきゃだめだ。欲しかったら、欲しい、って」
そんなことを言うなんて、そんなことをいままでにないくらい優しい声で言うなんて。
なにを言っているんだろう、と思い苦笑しつつもフェリックスは、けれどまっすぐに見上げてくるオリーブ色を見つめ返す。
そのとき、
「……いった……?」
不意に、訊ねられた。
ちいさな、消えそうなほどにちいさな声で、ジュードがはじめて口をきく。
そして、寒さのせいであるのか傷のせいであるのか掠れた声に訊ねられて、その手を包んだフェリックスの手がすこし震えた。
「……どこかの、だれかさんは……いったの……?」
悲しかったら、悲しい、と。
おまえは言ったのか、と。
そう訊ねられて、自嘲に頬を歪めた。
そんなこと、自分は言ったことなんてあっただろうか。
考えなくても、答えはわかっている。
魚の缶詰は食べたくない、と。
売らないでくれ、と。
自分を捨てた親に、言わなかった。
言えなかった。
「……ほしかったら、ほしい、って……」
ちゃんとこっちを見てよ、と。
ちゃんと愛してよ、と。
「いったら、くれた?」
くれるの、ではなく。
くれたのだろうか、と訊くジュード。
オリーブ色が揺らぎ、あっという間に、そこから深い憂いが溢れて白い頬をこぼれた。
それは、誰に向けた言葉なのかは、知れない。
どうしてジュードがあの路地裏にいたのかも、どうしてあんな格好でいたのかも、知れないけれど。
どうして、この世界には痛みが溢れているのだろうか。
傷ついて、傷ついて。
その果てに、どうして汚れながら融けなくてはいけないのか。
「……それは、わからない」
正直に答えると、ジュードの瞳があきらめたように逸れた。
だから、フェリックスは手を握る手に力を込める。
「僕は言わなかった。言えなかった。だから……言ってみようかと思うんだ」
「なにを?」
「そうだね……じゃあ、さしあたっては、きみに」
にこ、と笑いかけると、ふたたびジュードが首を傾げた。
「あのね、ジュード」
「…………」
「僕は『どこかのだれかさん』じゃないよ」
さらに笑みを深めると、それまで黙ってようすを見ていたギルバートとドロシーが、そろり、と不穏な空気を敏感に感じ取ったのか後ずさる。
両手を握りこまれて動けないジュードの頬が、ぴくり、と引き攣るように動いた。
「僕はフェリックスっていうんだよ。呼んでごらん」
ふるふる、とジュードは三角の耳を揺らしながら、必死に首を横に振る。
「どうして。ちゃんと言わないとだめだよ。ほぅら、『フェリックスおにいちゃん』っていってごらん」
ふっふっふ、と瞳を据わらせて笑うフェリックス。
それを遠巻きに眺めながら、ドロシーが隣に呆然と立つギルバートに言った。
「ねえ。なんだかフェリックスが……っていうか、あれってフェリックス?」
「……なにか、悪いモノでも乗り移ったんですかねぇ」
「ちょっとたのしそう?」
「いや、かなり楽しそうですね」
「司祭さま、よばなくていい?」
「呼ばなくても……いいんじゃないですか? ジュードには申し訳ないけれど、いまのところ僕らに被害はないんだから」
「そうなの?」
その会話は聞こえていたけれど、フェリックスは聞こえないふりをした。
事実、楽しかったからだ。
それからの日々は、ジュードをからかうことに費やしたと思う。
教会に世話になっている流れにまかせてこの町の女神に仕えるようになっても、それはやめなかった。
我ながら歪んでいるとは思う。
でも、やめる気はなかった。
なぜならそれは、ジュードには迷惑な一種の愛情表現で、自分にとっては必要な自己の確認だったから。
「ほぅら、おにいちゃんでちゅよぉ」
「………………やだ」
「どうせ誰かに嫌がらせでもしたんだろう?」
近頃教会の周辺で物騒なことが起こっているから、と身辺警護を頼んだとたん、疑われた。
「心外な。わたしがきみ以外の誰に嫌がらせをすると思っているんですか」
「…………一度死んでみたほうがいいんじゃないのか」
言うようになったなぁ、などと思いつつ、フェリックスはくつくつと喉を鳴らして笑う。
「生き返らせてくれるなら、考えないでもありませんが」
「そんなことできるわけがないだろう」
「それがそんなことができる物があるらしいですよ、魔術士たちの戯言ですけどね」
にこ、と作り笑いを浮かべながら言うと、Jが軽く眉を寄せた。
魔術士、という言葉に呆れたらしい。そんな存在など知らないのだろう。知ったところで、まったく興味を示さないに違いない。
現に、Jはすぐ興味を失ったらしく、半分ほど残した冷めたコーヒーをぼんやりと眺めている。
わずかに伏せられた長い睫毛の下にあるオリーブ色の瞳は、憂いを滲ませているもののあいかわらず澄んでいるらしい。稼ぎ屋などしているのだから、ひとの弱さも醜さも嫌というほど映しているだろうに。
「……欲しいものは、できましたか?」
ふと、訊ねてみる。
Jは一瞬、急になにを言い出すんだ、と眉を寄せたが、すぐにちいさく溜息をつき、
「べつに」
「べつに?」
「……なにもない」
教会を飛び出したときは、ジュードは馬鹿だと思った。
このままここにいるほうが楽に生きられるのに、と。
けれど同時に、羨ましくもあった。
そんな力、自分にはなかったから。
あれからジュードがどうなったかはわからなかったが、死んだ、と考えるほうが自然だった。あるいは、連れ去られて袋小路に売られるか。
生きていることがわかって、素直に嬉しかった。
この町の女神フィオナは身体を生かすためには便利な石の塊だったが、つついても無反応な相手はつまらないから。
けれど、きょうこのカフェの扉のまえで、フェリックスはわずかに躊躇したのだった。
ぬかるみは、雪を容赦なく汚らわしい色に融かしてしまう。
それを、知っていたから。
けれど彼は変わっていなかった。
それは喜ぶべき奇跡のようなものだったが、同時にすこし残念でもあった。
なぜなら。
教会から飛び出した彼も、過去の痛みからまだ抜け出せないままだったから。
フェリックスは、Jに聞こえるように深々と溜息をついた。
「……なんだ」
「つっまんないなぁ、と思いましてねぇ」
「は?」
「子守唄を歌って欲しい、とか言ってくだされば、遠慮なくその耳もとで唸ってさしあげるんですがねぇ」
「帰る」
短く言って、すこしばかり乱暴にJが立ち上がる。
それをわざとらしいつくり笑顔で見上げて、お代はこちらがもちますよ、と前置きし、
「では、明日からしばらくよろしくお願いしますよ、稼ぎ屋『J』」
すると、
「……なあ」
ふと、扉を押す途中、こちらを振り返らないままJが言った。
「どうしましたか」
「あんたはなんで……生きたがる。教会に、フィオナに媚を売って、稼ぎ屋に金を出してまで、なんでそんなに生きたいんだ」
「聞きたいんですか」
訊ねると、Jはちいさく溜息をつくらしい。
答えはおそらく、
「……いや、いい」
予想通りの返答に、コーヒー二杯分の代金を店主に支払い終えたフェリックスは、そっと苦笑した。
「Jは、生きたくないんですか?」
「俺は……」
「生きたい、ですよねぇ。長生きはできなくても……もうすこしくらいは。この先、どんなおもしろいものがあるかも知れませんし」
「おもしろい、もの?」
「大切なものかも知れませんよ」
ふふ、と笑いながら、Jが立ち止まったままの扉へと歩み寄る。
法服の白い袖が目のまえで揺れると、振り返った端正な顔がしかめられた。
相当嫌われているらしい。
案外、彼が教会を飛び出したのは自分のせいかも知れないな。
あれだけからかっていたのだから、当然か。
そう思いつつ、フェリックスはにっこり笑ってみせる。
すると、
「……すっかり『司祭』だな」
Jがくちびるを苦笑に歪めた。
「どういう意味です」
「あんたがそういうことを言うとは思わなかった」
「そうですねぇ。実はわたしも、これっぽっちも思っていませんでした」
「ジュード、泣かなくてもいいよ。だいじょうぶだから」
ちいさな『弟』は、よく夢を見て泣いていた。
とても痛くて悲しい夢のようで、いつも両手で自分の身体を抱きしめるようにして震えながら眠っていた。
だというのに、痛いも苦しいも言えず、うっすらと血が滲むほど幼いくちびるを噛み締める姿は、放っておくと儚く融けていきそうで。
すこしでも痛みをとってやりたくて、震える背中をさすりながら覚えたての子守唄をぎこちない調子で歌った。
それまでは覚える気すらなかった、誰かに歌うつもりなどなかった、子守唄。
それが聞こえていたのかいないのか、覚えているのかいないのか。
そんなことは知りようもないけれど。
しばらくすると、そっとこちらの袖を握って深い眠りに落ちた『弟』の寝顔は、たぶん。
あのころの自分にとって、なくてはならないものだったのかも知れない。
無意味にただ生きているだけではないのだと、そう思えたから。
「怖くないよ。だいじょうぶ」
それは『弟』と、そして自身に向ける言葉。
見えない塵を抱えていても。
綺麗な空ではないけれど。
あっけないほどすぐに消えてしまうのだろうけど。
それでも、もうすこしだけ。
生きていたい。
そう、願う。
|