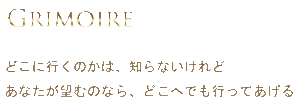
|
逡巡
 蜥蜴籠街(リザードケージ)は眠らない、汚れた町だ。
稼ぎ屋Jは、寒風吹き荒ぶ廃ビルの屋上、風を直に受けることを避けて入った給水タンクの陰から、迷路のように細長い闇をいくつもつくりだすけばけばしいネオンに埋もれるその町を、じっ、とオリーブ色の瞳で見下ろしていた。
すらりと長い右の手指は、いつでも銃を抜けるようにホルスターに掛かっている。
ネオンがうるさいあたりからは、機嫌の良い鼻歌に混じって罵声が。一層闇が濃いあたりからは派手に硝子が割られる音と悲鳴、そしてその合間には嬌声が。
ゴミ溜めのようなせせこましい箱庭のなか、多くの人間が短い命を抱えて這いずっている。
誰かを陥れて、誰かに踏みにじられて。
泥水を啜り、毒に溢れた世界で膝を抱える。
白い息を吐き出して、Jは目のまえの景色と容赦なく吹き付ける風とにちいさく身を竦ませた。
ちら、と腕時計を見やる。
予定より三十八分の遅れだ。
だが、すべての事象がこちらに都合よく進むわけではない。いや、そもそも時間というものを気にする人間自体、この町には少ないのだ。多少のズレは仕方ないだろう。
とはいえ、これ以上屋上にいるのは自分にとっても依頼人にとっても危険だった。
いざというとき、思うように銃が抜けなくては意味がない。
取引相手を待つ依頼人の身になにかあっては、護衛の依頼を請けたこちらの信用に関わる。腕利き、とこの町では多少は名が知られていても、周旋屋から仕事をまわされなくなってしまっては、生活に多大な支障を及ぼす。
ひとりなら、まだほんのわずかだが蓄えもあるからなんとかなるだろう。だが、いまのJはひとりではなかった。
食費がかさむ、というわけではない。
なにも食べなくても死んだりしないわ、と共に生きようと約した相手は言い、そしてそれは嘘ではなかった。
『死者の舞踏』
それが、相手のなまえ。
人の姿をした、人ではないもの。
だから食べる必要はないのだ、という。
だが、それではJの気がすまないのだ。
共に生きる、と言ったのだ。
生きる、というからには物ではない。
それなら、なにか食べたほうがいい、と思う。この町のことだ、美味い食べ物などはめったにないのだが、それでも食べることは生きることではないかと思うのだ。
しかし、
「……独りよがり、なのだろうか」
そんな風に思っているのは自分だけで、無理に食べさせようとすることは相手にとっては迷惑なことなのかも知れない。
この仕事が終わったら訊いてみようか。
ふと、そう思うところに、気配を感じた。
Jが給水タンクから離れて扉へと瞳をやると、依頼人とその屈強な使用人の間にさっと緊張が走る。
「ようやく来たらしい」
なにごともなく取引が終わってくれ、とJは表情ひとつ変えずに内心でつぶやいた。
はやく帰らないと、仮住まいの部屋に待たせている相手がまた不機嫌になってしまう。
しかしつぎの瞬間、きつく眉を寄せたJはホルスターから銃を抜いていた。
歩き出そうとしていた依頼人の肉の厚い腕を引き、給水タンクの陰に突き飛ばす。
突然のことに驚く依頼人の上げた声のあとに乾いた銃声がつづき、使用人の身体がぐらりと不自然に傾いだ。
Jは襲撃者にすばやく狙いをつけ、引鉄を引きつつ、
「……殺されるかもな」
ちら、といまこのとき目のまえにはない殺気に満ちて美しく輝く金の双眸を、思い浮かべていた。
どれほどに恨まれているのか、あるいは邪魔だと思われているのかは知らないし、知る必要もないが、雇われたらしいそこそこに腕のいい襲撃者数名から依頼主を無事に逃がしたあとは、無駄な弾の消費を避けるためJ自らも暗闇に姿を溶かした。
しばらく闇がつくる迷路のなかに息を潜め、こちらを追う気配が途絶えたころ、ようやくそこから抜け出す。そのあとすぐに部屋へと帰らなかったのにも、意味はある。用心に用心を重ねてのことだ。
それでも、部屋に戻る途中に通り過ぎた繁華街やその付近の路地裏で掛けられる艶めいた誘いは、すべてすげなく袖にした。
だというのに。
「っ!」
部屋に戻ったとたん、クッションが飛んできた。
扉越しにも不穏な空気は感じられたが、しかし、こちらが口を開くまえにこういった抗議がくるとはさすがに予想外。避け損なって、まともに顔で受けてしまった。
痛みはないものの多少驚きつつ、顔から落ちてくるクッションを左手で受け止めると、Jは深々と溜息をつく。
「そんなものさえ避けられないなんて、呆れるわね。それでよく稼ぎ屋なんてしているわ」
ふ、と薄暗い部屋のなかで禍々しいほどに輝く包帯で隠されていない右だけの金の瞳に、微弱ながらも殺気すら浮かべて、鋭く女が言い放った。
「…………そうだな。これがナイフだったら、死んでいたかも知れないな」
素直に認め吐息で言うと、長く待たされたために不機嫌だった女の態度がわずかに軟化したようだ。殺気が消えて、かたちの良い薄紅色のくちびるが暗く甘い笑みにつりあがる。
「だいじょうぶよ。あなたが死んでしまったら、わたしがちゃんと蘇らせてあげるわ」
そう得意気に言うこの女こそが『死者の舞踏』。死者を蘇らせそれを隷属させるという、忌まわしき闇の魔道書だ。
凶暴な呪文(スペル)が記された顔の左を包帯で隠していても隠し切れない、人にあらざる凄絶な美貌。つくりのひとつひとつは繊細だというのに、清らかな女神と賞する美しさかというよりはやはり、深い闇へと誘う妖艶な魔のそれ。
昏くも甘く笑まれたなら、美しさの分だけ凄みも増すというもの。それは身体の弱い老人や子どもなどはあっという間に鼓動を止めてしまうかも知れないほどではあったが、あいにくJはすでにその顔に耐性ができていた。
そのため、ほんの軽く肩をすくめてみせただけで部屋の奥へと進み、隅にあるベッドへとクッションを放り投げる。
「わたしは『死者の舞踏』。蘇らせることができない屍なんてないわ。あなたのことも、生きていたときとおなじ姿で蘇らせてあげる。ねえ、J。そうしたらわたしがずっとそばにいてあげるわ。朝も昼も夜も、ずっとよ。どう? 嬉しいでしょう」
ちょっとは嬉しそうに笑ってみてはどう、とこちらの腕にしなやかな細い腕を絡めてきた女に頬をつつかれるが、Jはテーブルの上に視線をやったままちいさく眉を寄せ、答えなかった。
テーブルの上は、仕事のためにこの部屋を出た際となんら変わらない。
なにも、減ってはいなかった。
缶詰はひとつも開けられたようすもなく積まれたまま。
昼間に購入したパンは乾いて転がっている。
乾燥したナッツも袋に入ったままだ。
窓の外のネオンに照らされるだけの薄暗いなか、物悲しく。
手をつけられていないそれらを眺めて、Jは静かに睫毛を伏せた。
なんとなく。
ただなんとなく、だ。
「J、どうかしたの」
黙っていると、ふと女がこちらを覗き込んできた。
その拍子に、さら、と光沢のある鮮やかな赤紫の長い髪が細い肩の上を流れる。
やわらかな毛先に腕をくすぐられて、思わず眉を寄せた。
思わず絡められた腕を解こうとその手首を掴んで、しかし、やめる。
「J?」
ひんやりと冷たい、氷雪のような肌。
じわり、とその冷たさが胸に染みるようだった。
「どうしたの、J。いまにも泣き出しそうな子どもみたいな顔だわ」
つ、と頬の輪郭を指先でなぞられて、Jはゆっくりと睫毛を伏せる。
体温がないわけではない。掴んだままでいると、じんわりと肌の下からぬくもりが伝わってくる。だが、それでもやはり女の体温は低かった。
「誰かに苛められたのかしら。だってあなた……硝煙と血の匂いがするわ。誰に苛められたのかしら。教えてくれるなら、その誰かを呪い殺してあげる」
「その必要はない。そもそも、俺は苛められたわけじゃない。仕事だ」
「だったらどうしてそんな顔をしているの。わたしに帰るのが遅いと怒られて、泣きたくなった?」
俺は子どもじゃない、と言い掛けたJはしかし、口を噤むとちいさく溜息をつく。
そう言えば、五百年以上まえに著された魔道書はこう言うに決まっているのだ。
わたしに比べれば、あなたなんて子ども。
そしてそれになにか言い返したとしても、結局こちらが言い負かされるだろう。
不毛だ。
結果の見えた会話を楽しむこともないわけではないが、いまはそんな気分でもない。続ければ続けるだけ虚しくなるだろう。
おかしい。
自分のことだというのに、なぜこれほど気分が沈むのかがわからない。
気のせいか、身体までも泥を纏わりつかせたかのように、重い。
感傷だとでもいうのか。
けれど、いったいなにに対して。
いや、理由はわかる、と思う。だが、たいした理由でもないし、いまにはじまったことではない。
だというのに、なぜ。
「そんなに悲しい?」
「……なに」
「わたしに怒られて」
どことなく嬉しそうに見える金の双眸から、そうじゃない、と瞳を逸らす。
その細い肩の、むこう。
置き去りにされたのは、テーブルの上のものなのか。それとも……。
そのときだ。
すい、と冷たい手指が伸びてきて、こちらの瞳にかかるほどに伸びた前髪を梳くようにかき上げた。
つられるようにふたたびそちらに瞳をやると、目のまえで不思議な色の髪が揺れ、なぜか不安げに光る瞳に出会う。
染みひとつない頬はわずかに歪み、羽根扇のように長い睫毛が室内に流れ込むネオンの光を絡ませながら震えていた。
思いがけないことに、理由も知れないまま胸の奥がずきりと痛む。
「……J、変だわ」
ぽつんと言われた言葉に、え、とJが軽く眉を寄せると、女は潤んだような瞳でじっとこちらの瞳を覗きこむように見つめてきた。
「どうしたの」
問われて、逡巡する。ややあって口を開こうとするが、不意に重い眩暈を覚えてさらに眉を寄せた。
「J!」
「……ぁ……?」
慌てたように呼ばれて、自分の身体が傾いだのに気付く。情けなく床に膝をつきかけるところを細い身体に支えられて、ぼんやりと美しい顔を間近に見つめた。
すると、それがゆっくりと近づいてきて、ふわ、と甘やかな吐息が頬に触れる。
反射的に瞳を閉じると、こつん、とこちらの額に額が当てられた。
包帯越しでもひんやりとしたそれに、思考が流される。
そうしていると眩暈が和らぐようで、しばらくこのままでいいか、と抗うことなくじっとおとなしくしていた。
しかし、
「J。あなた……熱があるわよ?」
すんなりと離れていく額に、むっとする。
熱があるのは当然だ。生きているのだから。
だいたい、食べないからそんなに体温が低いのだ。
「……なんで……食べないんだ」
腹立ちついでにぼそりとつぶやくと、え、と女は金の瞳を瞬かせた。
当然だ、相手にしてみれば唐突過ぎる。だがJにしてみれば、ここしばらく思っていたことなのだ。少々、口にするのが遅いほどに。
「食べない、ってなに」
「おまえは、なんで食べないんだ」
答えはわかっている。
わたしは魔道書。食べなくたって死んだりしないわ。
そう言うに決まっている。
それなのにわざわざ訊くなんて。
自嘲に、Jはくちびるを歪めようとした。けれどできずに、溜息を落とす。
すると、
「あなたが帰ってから一緒に食べようと思ったからよ」
とっさになにを言われたのかが理解できずに、Jは半ば呆然と、不機嫌だというのにどこかやさしげでもある複雑な表情をしている女を見つめた。
「それなのに、Jったら帰ってくるのが遅いのだもの。待っていてあげるとは言ったけれど、それは信頼の現われというものだとは思うけれど、でも、硝煙と血の匂いを絡ませて予定よりもずっと遅く帰ってきたら、怒るに決まっているでしょう。しかも、いつもより体温が高い。異常に! こんなことなら、呪文(スペル)にあなたの見張りをさせておくんだったわ」
「……異常、に?」
「そうよ。熱がある、と言ったでしょう?」
「……おまえの体温が低いんじゃ……」
「わたしの体温は確かにあなたよりもいつも低いけれど、違うわ。あなたの体温はいま、異常に高い」
自分でわからないの、と呆れられて、絶句する。
確かに、寒風にさらされたが。
けれどさきほどまでは、なんでもなかったというのに。
熱など、出したことはないとはいわないが、身体も鍛えているためさほど縁のないものだというのに。
「……な……」
「いいわ。あなた、自分のことには疎いもの」
「は……?」
「わたしがちゃんとそばにいて、看病してあげる。あぁ、そうだ。呪文にも手伝わせようかしら。添い寝なんて、どう。寒いなら黒い呪文のふさふさの毛並みがちょうど良いし、冷やすなら赤い呪文の鱗がひんやりしてちょうど良いわ」
ふふふ、と手指を薄紅色のくちびるに寄せて暗く甘い笑み声を吐く女に、Jの背に悪寒が走った。
黒い呪文。『死者の舞踏』第一の呪文『喉と腸(はらわた)を食い破る、残忍なる黒き獣』は、まあいい。見慣れた。あれはちょっと身体の大きな犬だと思える。
だが。
硬いのかやわらかいのかよくわからない鱗に覆われた、あの鞭のような生物。蚯蚓(みみず)などのちいさなものでさえも寒気がするというのに、『死者の舞踏』第二の呪文『首を圧し折る、鋭き牙の赤き毒蛇』は、恐ろしく長大な上に滴る血のように赤い。
あれと添い寝など、考えたくもない。
Jは、さきほどよりも力の入らない腕を無理に動かし、女の身体をなるべくそっと離す。無言でベッドに逃げようとしたが、ぐい、とコートの襟を掴まれた。
ぎこちなく振り返ると、やさしすぎるほどやさしい笑みを浮かべた女。
「どうしたの、J。コートも着たまま、ホルスターも外さないで」
「…………」
「そんなに呪文と添い寝がいや? それならわたしがしてあげましょうか」
に、と笑みが深められ、その美貌に凄みが増した。
これは確かに、心臓に悪いかも知れない。知らない間に呪われて壊れてしまったのか、身体のなかでうるさく鳴る鼓動は痛いほどだ。
そう思いつつ、Jは首を横に振った。
「あら、どうして。嬉しいでしょう?」
「断る」
「あら。熱が上がったのかしら。顔が真っ赤だわ」
「……うるさい。黙っていろ」
「いいじゃないの、喋っていても。あなたはわたしの声を子守唄代わりに、おとなしく眠ればいいの。でも、そのまえに……なにか食べる?」
くす、と薄紅色のかたち良いくちびるから笑みがこぼれて、自然に瞳を奪われる。
とたんに、するり、と胸の痞(つか)えがとれるのを、おかしく思った。それだけのことで、気分が楽になったような気さえする。
それほどに自分は気にしていたのだろうか、と思う。
だが、
「あなたが望むなら、食べさせてあげてもいいわよ? 口移しで」
「っ! もう、いい……!」
ふたたび襲う眩暈に加えて、頭痛までしてきた。このままではじわじわと殺される。
Jは力が抜けそうになる膝に舌打ちしつつ、楽しげな笑み声を鈴のように転がす女に背を向け、少々乱暴にコートを脱いで細い腰に下げたホルスターを外す。
「J」
ベッドに潜り込もうとするところに声を掛けられて、なんだ、とそちらを見もせずに言うと、女が近寄る足音を聞いた。
さら、と髪を手指で梳かれて、眉を寄せたまま軽く睨むように瞳をやると、
「熱が下がったら、なにか美味しいものをつくってちょうだい。一緒に食べましょう?」
「…………わかった」
「おやすみなさい、J」
目蓋をそっと、ひんやりとした手指に覆われる。
とたんに身体から、すっ、と力が抜けた。
おやすみ、と返せたかどうかはわからないが、穏やかに遠ざかる意識のなかで女の声を聞く。
「ねえ、J。そんなに心配しなくても、わたしは約束をやぶったりなんてしないわよ?」
またからかわれた、とは思ったが、だから、腹も立たなかった。
それでもいい、と思う。
以前は、食べること以外に、痛みを感じることで生を感じていた。だから稼ぎ屋などというものをやっているのだ。
けれどいまは、
もうひとつ。
だから。
深い闇と派手なネオン。
年中雲に覆われた灰色の空と、腐臭を散らすゴミの山に汚れた町。
それでもまだ、ここで共に生きようと思う。
|